|
仕事熱心な若者が、ある日突然この世を去った。最愛の息子を亡くした母は、なぜ息子は命を落とさなければならなかったのかと問い、裁判をはじめる。互いを思いやる家族の絆は、彼の死によって途切れてしまうのか。
受話器から流れてくる石井淳子の語り口は明瞭かつ軽やかで、まるで同年代の女性と話しているような錯覚に陥るほどだった。息子に先立たれた母親の悲しみを切々と訴えることもない。私はふっと安堵感を覚え、心のうちにしまっておいた言葉を口にした。
「亡くなるまでの数ヵ月、はたから見ても、偉(いさむ)さんは量的にも質的にもオーバーワークだったように思います」
すると、淳子の口調が変わった。
「実は私も、仕事による過労ではないかと思っております」
それまでの軽やかさとは対照的に、重く響くものがあった。そして、こう続けた。
「遺品の中に日記はおろか、手帳もないため、あの子がどんな仕事をしていたのかさえわかりません。リクルートに聞いても要領を得ないので、弁護士さんにお願いして、文章で仕事内容や労働実態を問い合わせてもらいました。そしたら、回答書がきたのですが、そこには偉が好き勝手に残業をしていたのであり、それは本人の能力が低いからだというようなことが書いてあって・・・」
聞いた瞬間、怒りがこみあげた。
「それは事実とは違います。偉さんがどれほど優秀な編集者であったか、細やかな心づかいができる人間であったか、私は知っています。インターネットが今ほど普及していない中で、「Digital B-ing」という新しいメディアを立ち上げるために、相当な無理をしていたことも。私が知っていることはすべてお話しましょう。お母さん、東京に出て来られませんか」
間髪いれず、淳子は答えた。
「行きます。東京へ」
お金はいらない。真実が知りたい。
それからまもなく、淳子は上京してきた。待ち合わせ場所の、私が住んでいる京王多摩センター駅(東京・多摩市)に着くと、スーツ姿に大きなバックを手にさげた女性が微笑みながら近づいてくる。
「旭川ではもうコートが手放せないのに、東京は暖かいですね」
ていねいで柔らかい物腰は、電話での会話から想像していた人柄と重なりあった。
淳子は偉が亡くなってからのことを話した。
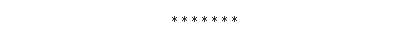
葬儀が終わってから茫然自失の日が続いてはいたが、偉の死は過労死ではないかという思いが胸の底で重低音のように響いていた。しかし、リクルートに労働組合はなく、確かめるすべがない。知人の弁護士などに相談してはみたものの、具体的な方向性が定まらなかった。
逡巡していた1996年12月のある日、新聞で「団体生命110番」の記事を見た。その時、偉の葬儀後、リクルートから「団体生命をかけているのでお支払いしたい」と送られてきた団体生命保険の書類のことを思い出した。「我が子の命と引き換えのお金など受け取りたくない」、そんな抵抗を感じていたため、まだ返送していない。藁にもすがる思いで、札幌の弁護士たちがボランティアで開いている「団体生命110番」に電話をかけた。
電話に出た担当の弁護士は話を聞いて「詳しくお話をうかがいましょう。札幌に出てこられますか」と訪ねる。淳子は「すぐ、行きます」と翌日、札幌に向かい、それまでのいきさつを伝えた。すると弁護士は言った。
「お母さん、息子さんは過労死だと思いませんか」
「まさに、そう思っています。あの子の労働実態を調べたいんです」
「僕が引き受けましょうか」
「ぜひ、お願いします」
「弁護団を組みます。過労死を手がけている仲間が東京にいますからご紹介しましょう」
一方、淳子が弁護士に相談したことは、偶然のいたずらか、リクルートが知ることとなった。
淳子は、リクルートで偉の先輩だったジャーナリストの河村清明と、偉の死後も連絡を取り合うことが多かった。偉とプライベートの付き合いも深かった河村は、偉が好きだった場所や飲食店などに淳子を招待するなど、親身になって気をかけてくれた。それだけに、弁護士に相談したいと思ったとき、真っ先に河村のことが気になった。かつて勤めていたリクルートを相手に弁護士をたてることは、河村を不快な気持ちにさせはしないか、と。河村は「気にしない」と言ってくれた。だから、実際に弁護士に相談したことを、河村に打ち明けた。
河村は、淳子から聞いた話をアメリカに滞在していた元同僚の女性にメールで伝えた。すでにリクルートを退社したその女性も、偉の死を心から悼んでいたからだ。そして、彼女がメールを開いているところに、ちょうど渡米していたリクルートの社員が居合わせ、メールを読み、その社員が会社に報告したのだった。
弁護士に相談すると、会社の人間がやってきた
翌97年1月、淳子のもとに偉の上司だった田中和彦から突然「お線香をあげたいので、うかがいたいのですが」と電話がかかってきた。1月の旭川は一年で最も寒さが厳しい。葬儀が終わってからというもの、リクルート社員の誰からも個人的な電話一本、はがき一枚すらないというのに、厳寒のこの時期になぜ? 淳子は「弁護士に相談したことが伝わったな」とピンときた。ていねいな口調で断ったが、押し切られた。やがて、旭川を訪れた田中は言った。
「何もいきなり弁護士に相談しなくても」
淳子には批判めいて聞こえ、こう言い返した。
「リクルートは労働組合がないですよね。どなたからも連絡がない中で、どこに相談したらいいんですか」
2月、再び田中が来訪する。人事部の人間も同行した。「もうしわけない」と詫びる姿勢のなかにも、さり気なく、
「弁護士に相談したことを社員たちが知り、『じゃあ、私たちがしてやったことは何だったのよ』と言っています」
といった話を、社員の実名をあげながら散りばめる。「してやったこと」とは、葬儀を手伝ったことを指していた。
労災申請をしたわけでも、裁判に訴えたわけでもないのに、弁護士に相談をしただけで許せないのか。淳子は、社員の間に流れる空気が変わったことを知り、そして、悩んだ。息子が自分で選んで入った会社で、希望の仕事をのびのびやらせてもらって、とても良い人間関係の中にいたのに、その思い出をぶち壊しにするのではないか、と。だが、結果的に、これを機に真相究明に向けた家族の結束は強まっていく。
3月、のちに主任弁護士となる玉木一成と会い、ことの一部始終を話した結果、裁判所への提訴も念頭におきながら、労災申請の準備を進めることを決めた。だが、労働実態を示す証拠はあまりにも少ない。労災申請は会社の同意がなくても行えるものの、会社が「過重労働があった」と認め、協力的であればあるほど、労災認定もおりやすい。しかし、会社の協力は得られそうにない気配だった。
それから事態は、ほとんど進展することなく、時間だけが経過していった。8月の一周忌が過ぎた頃、偉の妹のまどかの妊娠を知る。悲しみが消えることはないが、初孫が生まれる喜びとあわただしさの中でその年はあっという間に過ぎ去る。
98年2月、淳子は20年余り続けてきた法律書の加除の仕事を辞めた。体調がすぐれないこともあったが、「裁判を起こしても、決着をつけたい。そのためには仕事を続けるのは無理だ」と判断したからだった。
8月、偉の3回忌を前に、リクルートの同僚たちが『ごはんたべにいきませんか』という手づくりの遺稿集を作った。偉とゆかりのあった社員、フリーのライター、カメラマン、デザイナーたちが思い出をつづっている。それを手にした淳子は一人一人の熱い思いを知り、涙があふれた。リクルートという会社に対しては不信感があるが、偉の友人たちには感謝の気持ちでいっぱいだ。
同時に、自分も偉の遺稿集を作りたいと思った。『ごはんたべにいきませんか』はリクルートにいた4年半の記録しかない。生まれてから亡くなるまでの29年の遺稿集を作ろう、と。
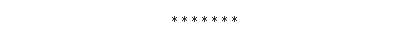 母の悲しみ、母の闘い
「それでね、偉が書いたものがないだろうかと遺品を整理していたの。名刺ファイルを開けて、この人はカメラマン、この人はライターさんと整理していたら、渥美さんの名刺が出てきたんです。出版社の名刺だったから、もしかして偉が原稿を書いているかもしれないと、渥美さんの名前が気になってね、名刺の裏をみたら、ご自宅の電話番号が書いてあったの。それを見たとき、一言も言えずに逝ってしまったあの子が『母さん、この人に電話をしてごらん。きっと力を貸してくれるよ』と言っている、そう感じて、お電話したんです」
最愛の息子を亡くした母親が、すべてを投げうってでも、息子の名誉にかけて真相を究明し、全身で立ち向かおうとする姿は胸をうつものがあった。すでに8月末に、中央労働基準監督署に労災申請の手続きは終え、次は裁判所への提訴を考えていると聞き、私は協力を約束し、別れた。
11月26日、淳子は再び上京してきた。「話をする時間が欲しいから」とわざわざ都心から京王多摩センター駅まで来た淳子とともに、東京・千代田区にある玉木弁護士の事務所に向かった。私の知っている事実を弁護士に伝えるために。
電車の座席に2人並んで腰を降ろし、都心までの約1時間、いつしか話は淳子の数奇な人生をたどっていた。人間関係や貧しさに翻弄された子ども時代、夢見た結婚生活の破綻、そして苦労の末にようやく手にした親子3人での幸せな日々のこと。ひとつひとつの話が胸をうつ。
「子育てで大切なことって、お金があるなしや、子どもと一緒にいる時間の長さじゃないと思うのね。一生懸命に生きている姿を子どもに見せること。いつも、子どもを受け止め、理解し、信頼してあげる事だと思うの。それがあれば、子どもは素直に育つものなのね」
偉はもうこの世にはいない。それでもなお、淳子は偉を理解し、信頼して、前途を閉ざされた偉に代わり真相究明に向かおうとする。母とは、かくも悲しきものなのか、そして、かくもありがたきものなのか。
やがて、都営新宿線の車内アナウンスが弁護士事務所のある小川町駅についたことを告げた。
(敬称略、つづく)
|