|
冷戦が終わり、諍いも隔たりもない世界が広がる。そんな風に考えたのもつかの間、人々は以前よりも内向きに、自らの殻、国家や民族に閉じこもり始めた。これは一時的な反動なのだろうか。それとも、こうした息苦しさはこれからも続くのか。人々が国家や民族、人種という鎧を剥ぎ取り、自分自身になれる時代はやってくるのか。ジャーナリスト藤原章生氏が、世界各地の現場から、さまざまな人間との出会い、対話を通して考察する。
「彼は自分の世界を持っているから」
よくこんな言葉で人を褒めることがある。これは、滅多に人を褒めない知人があるジャーナリストを評した言葉だった。「世界」というのもずい分あいまいな言い方だが、信念のような意味合いだろう。なぜなら、そのジャーナリストは結構、辛口というか、思ったことをずばずば書く癖のあるタイプだからだ。彼は、日米関係にせよ、国際情勢にせよ、一家言あるということを言いたかったようだ。
しっかりと自分の世界を持つというのはいい面もあるが、それが自分の中で完結してしまうと、考え方の違う他人との対話が成立しない弱みになる。
昨年、米国のフロリダ州で知り合ったジムという男に私は「完結した世界」の融通のなさを感じた。善意の人であり、常に他人のために何かしようと心がけているのに、批判されるともろい。いや批判そのものを受けつけない。
ジムは一言で言えば「宗教右派」「キリスト教福音派」などと呼ばれる米国人の中の一つの典型といえる人物だ。
 |
ジムとジーン
04年10月 引退者村ナルクレスト |
ジムとジーン。50代半ばの夫妻に会ったのは、元郵便局員が集まるフロリダ中部の引退村、ナルクレストだった。月刊誌『ナショナル・ジオグラフィック』の連載企画「郵便番号(ZIP CODE)」にこの村の話が載っていた。村には郵便配達員の敵でもある犬が一匹もいないという話が印象的で、04年10月米大統領選の仕事を兼ね、村を訪ねてみた。
村に入る前、腹ごしらえをしようと、平原にポツンとあるハンバーガー店「ウェンディーズ」に入った。店に入ったのは私の仕事を手伝うキューバ系米国人と在米メキシコ人、それに私を加えた男3人だった。
米国はラテンアメリカに比べ開放的に思えるところがある。というのは、あらゆる人種、民族がごったに暮らしているという前提がある分、新参者の外国人でも、まるでその土地に長年住んでいるような気分になれるからだ。それは他の国にはない特徴だろう。ラテンアメリカでもブラジルをはじめとした南米諸国の場合、そういう空気があることはあるが、米国ほどではない。
メキシコの場合、米国とは明らかに違う。「互いの顔つきを見ただけですぐにメキシコ人だとわかる」(『遠い隣人』アラン・ライディング著)※という暗黙の了解のようなものが国民の間にあり、よそ者が現われると、すぐに察知されてしまう。それは時に歓迎であったり緊張だったりするが、少なくともその場が、「よそ者の到来」を集団で察知しているのは確かだ。
 |
「ここは楽園のようでしょ」
と住人たちが口々に語る
04年10月 ナルクレスト |
ただ、その平原のウェンディーズに入ったときだけは、いくら米国でも我々3人は自分たちが明らかに異質だと認めざるを得なかった。そこにいた客の大半は、一人で来ている老人たちか初老のカップルで、店員はいずれも20代から30代のアフリカ系の女性だった。
調理場の方から時折店員たちのけたたましい笑い声が聞こえてくるが、老人たちで占められた客室は異様なほど静かだった。私たちはよそ者らしく、静かにスペイン語で話をしていたが、周りでは時おりぼそぼそとした英語の音が聞こえるだけだった。
カサカサというハンバーガーの包みを開く音、ハンバーガーをゆっくりもぐもぐと噛むときに鳴る微かな、コツコツという入れ歯の音だけが妙に響く。この辺りに他にレストランはない。一人で食べている老人が多いのは、配偶者を失くしたせいか。それとも、もともと独身が多いのだろうか。ただ、気軽に胃袋に食事を収めるだけとはいえ、なんだかわびしい。
「世界一さびしいウェンディーズ」という言葉が頭に浮かんだ。
ほどなく会ったジムとジーン夫妻は、「私たちの町を、私たちの国を美しくしましょう」と書かれた、真っ白いおそろいのTシャツを着ていた。一人近づいていった私にジムはずい分と顔を近づけ、熱心にこちらの意図を聞いた。目を合わせないので、すぐに盲人だとわかった。20歳のとき、事故で失明し、郵便局を早めに引退してフロリダにやってきたそうだ。子供が3人いるジーンは再婚で、2人は結婚してさして年月はたっていない。
イラクの話を持ち出すと、ジムはよく響く声で話し始めた。言葉を交わすというのではない。一人主張するという語りだ。
「いまは大変なときだ。罪もないアメリカ人が異教徒の野蛮人に首を切られたりしている。でも、彼らもいずれわかる時が来る。我々が彼らの自由のためにどれだけ努力しているか。普通のイラク人の大半は我々アメリカ人に感謝しているらしいし」
「そうでもないんじゃないですか」
そう口を挟むと、ジムは心外だという顔をした。
「何でそう言えるんだい」
 |
路上で車を待つ女性たち
04年10月 マイアミビーチ |
イラク戦争後、現地に3度行ったことを告げると、ジムは少し居住まいを正した。
「で、どうなんだい。イラクの様子は」
「戦争直後、人々はいまより希望を持っていたし、米兵にも親しげだった。でも、いまはとてもそんな風じゃない。イラク人のアメリカを見る目は行くたびに悪くなっている」
そう告げると、ジムはいとも簡単にこう答えた。
「そうだろうね。でも、イラク人たちは誰も独裁者の時代に戻りたいなんて思っていないだろ。些細なことで拷問を受け、盗んだだけで腕を切り落とされる。そんなサダムの時代から彼らを解放してやったのは我々アメリカ人だ。それが一番わかっているのはイラク人だよ」
「でも、そう思わない人々が意外に多い。だから抵抗が続いているわけだし」
「そうだろうね」
ジムとの話は堂々巡りだ。こちらが現地の話をすると、「そうだろうね」とうなずくが、「でも」と付け加え、すぐに持論に戻してしまう。
「自分たちは公正な選挙で投票できて、しかもその票をきちんと数えてもらえて幸せだと思うね。その我々がいま無知な異教徒たちに投票する喜びをもたらすため、自ら命を落としている。こんなことをしてやれるのはアメリカ人くらいだろうね」
だけど多くのイラク人は感謝していない。余計なおせっかいを、と思っている人も結構いる。それに、すぐに陰謀論を説きたがる彼らの多くはアメリカが駐留する狙いはもっと別のところにあると思い込んでいる。
そんなことを言っても話は同じだろうと思い、私は黙っていた。
「じゃあ、写真を」
と、夫妻を人口沼にかかる橋へと促すと、とつぜん夕暮れの強い風が吹いてきた。それに促されるようにジムが神の話を始めた。
「君は神を信じるかい」
「それが神かどうかはわからないが、何か得体の知れない、いまの科学ではうまく計れないエネルギーのようなものがあるということは信じる」
「それが神だよ。だから君は神を信じているわけだ。では、ジーザスは神の子だと信じるかい」
「それはわからないな。ただ、その得体の知れないエネルギーをうまく操るか、感知できる人間だったと思うけどね。いわゆる霊的な人間と呼んでもいいけど」
「いや彼こそは神の息子。つまり彼は人間の形をした神なんだ」
「そう言われるとどうもね」
そう言いながら私は夫妻の写真を何枚か撮った。
「霊的な人間は世界に無数にいる。あらゆるクラブ、宗教をまたいで彼らは現われる。ジーザスはその中でも特にその力が強かった。そういうことじゃないのかな」
そう進言すると、ジムはこう言い募った。
「いや、ジーザスがただ一人の神の子だ。彼は預言者でも何でもない。ムハンマドは預言者で、彼はただの人間だ。だから毒を盛られて死んだんだ。もう生きていない。でもジーザスは人間じゃない。彼は神の子だ。だからいまでも生きているんだ」
「聖書を読んだらいいわよ」
脇からジーンが口ぞえした。私は以前、聖書を読んだが、どうも、信じられない部分も多く、信仰にはつながらなかったと告げるとジムはたたみかけるように、
「自分はとても分析好きな人間だと思うけど、信仰ってのは分析で得られるものじゃない。まず信じることだ。我々は信仰を通して救われるんだ。君、自分が悪い人間だと思うことあるかい」
「あるね、しょっちゅうだ」
「その通り。君は悪い人間だった。僕も悪人だった。でも、こうしていまも生かされている。何のために? いい人間になるためさ。それは誰が決めている? ジーザスだよ。ジーザスは君や僕の罪をかぶってくれているんだ。そして、我々をいい人間にしてくれるんだ。でもそのためにはジーザスを信じなくちゃ。そしたら我々は平和な気持ちになり、いつも自信を持っていられる」
 |
自家製3輪車で通り過ぎる男性
04年10月 デイトナビーチ |
そして何を思ったのか、ジムはこうつけ加えた。
「君は日本人であることを恥じることはない。誰も君が日本人だからといっていじめることはない。ジーザスを信じれば、そんなことはどうでもいいことだ。大事なのは心を平和にすることだ」
なぜ、彼は私の国籍に触れたのだろう。私の話し振りに自信のなさを感じ取ったのか。そして、それが私の国籍、人種から来ていると彼は読んだのか。
一人話し続ける彼がこう言ったとき、その答えがわかった。
「自分はアメリカに生まれて幸せだと思う」
脇にひかえるジーンも復唱した。
「私もアメリカに生まれて幸せ」
「なぜなら、この土地は神が最も祝福する恵み多き地だからだ。ここにいれば、我々は最も神に近いところにいられる。だから人々はみなこの国に来たがるんだ」
つまり、彼は、アメリカ人ではない私に同情したのだ。というよりも、彼が失明した33年前、20歳のときに目にした日本人に同情しているのかも知れない。
「それまで見えていた。それが突然、何も見えなくなった。ひどい気分だったよ。自殺も考えた。でも、そのときジーザスのことがわかったんだ。彼がこうしたんだ。目が見えなくなったのも彼の導きだとわかったら、気分が落ち着いた。それに従えばいいんだと。そしたら、自分は天国に行けるんだとわかったからね・・・」
 |
ハリケーン後の海岸を見に来た家族
04年10月 東海岸デイトナビーチ |
夫妻と別れ、我々は再び「世界一さびしいウェンディーズ」の方へと車を走らせ、帰っていった。
それから3日とあけず、ジム夫妻から電子メールが届く。聖書の中の読むべき章を紹介したものや、同じ仲間からの便りを添付したものなど。そこには一言、「愛」だとか「ジーザスは神の子」と書いてある。
私はあるとき、彼とイラクについてもう少し対話をしたいと思い、米軍のクラスター爆弾で子供6人を失ったイラク人夫妻について私が書いた記事(注)の翻訳を送った。
はるか彼方の他人の不幸に思いを馳せるのは簡単ではない。まして、フロリダという楽園のような土地に暮らしていると、砂埃舞うイラクで何が起きたのかを考えるのは容易でない。私自身もイラクに行かなければ、さほどの思い入れはなかったろう。そう思い、ジムの意見を聞いてみたかった。
彼の返事は厳しいものだった。
「君はイラクでその夫妻をインタビューする前に、サダムの拷問室に行ったのかい。サダムに両腕を切り落とされた人の話を聞いたのかい?」
そんな内容だったので、イラクの話はこれ以上続けられないことがわかった。その話は彼の中でもう完結してしまっている。だとすれば私とは話が通じない。対話が成立しない。多分、ジーザスはいるのだろう。そう信じるようにしよう。そして自分はいい人間だと思うようにしよう。でも、話がそれ以上続かないんじゃ仕方がない。
 |
テールランプが映える夕暮れ
04年10月 デイトナビーチ |
年末、ジーンからメールが届いた。津波について記されていた。
「多くの人は、何の警告もなしに、ジーザスが救世主だと知ることもなしに死んでいった。もしあなたの家族が救世主ジーザスを知らないなら、どうか、彼らにどれだけそれが大事かって知らせてほしい。私たちはいつ自分の生が終わるかわからない。いろんなことが世界で起きて、段々悪くなっている。聖書は『その日』に向け、地震が増えると伝えている。私たちはいま世界の終わりの中で日々を過ごしている。そして、神の子たちを天国へ連れて行くため、ジーザスはいつでもやってきてくれる。あなた方みんなに、私たちと一緒に来てほしい。あなたの子供たちも。ジーザスが神だと早く知れば知るほどいい。そうすれば神はあなたの子供たちを救ってくれる。どうか、早く」
私は何も返事をしないまま、ただメールを放ってある。
(敬称略、つづく)
(注) 毎日新聞03年9月12日の記事
 -「バビロンの楽園(上)」草稿 -「バビロンの楽園(上)」草稿
逃げ惑うというのではなかった。リュックサックを背負った子供たちは手をつなぎ、土埃の立つ道をただ走った。小さな弟は普段と違う行動が嬉しいのか、笑っていたという。家を出てほんの数分、乾いた川のほとりで、家族8人は一斉に吹き飛ばされた。
3月31日午前10時過ぎ。バビロン州の町ヒッラの外れにある500戸ほどの集落、ナダルの上空で爆音が聞こえ始めた。大きな筒が空中で破裂し、子爆弾が破裂音と共に一帯に広がった。住民は後に米軍のクラスター爆弾だと知らされた。
砂の上に吹き飛ばされた家族8人のうち幼い者が先に逝った。次男のアンワル君(12)、次女ナバさん(9)、三男モハメド君(5)。生後55日目のヤコブちゃんも即死だった。頭や胸に子爆弾やその破片を受けた。
「長男のアリ(13)と長女のヌウォー(12)は1時間苦しんだ。泣き叫びながら死んでいった。川に吹き飛ばれた私は妻に引き上げられたが、痛みと、足が動かずどうすることもできなかった」
父、アブドゥル・ジャワド・ナーマさん(46)は自宅の暗い土間でそう語った。自身も左足の指2本を失い胸や肩に幾つもの傷を残した。
妻、アリアさん(30)は身ごもったばかりの胎児を病院で失った。「妻は体は戻ったが、心はひどいものだ。日本でもアメリカでも行って聞いてみたらいい。6人の子供を一遍に目の前で殺された親がどんな気持ちがするかと」「最初、ヘリコプターの音がした。何かの合図と思い、大丈夫だと皆で外に出た。あのまま家にいれば」
旧約聖書のアブラハムの孫ヤコブから名づけられた乳児の写真は翌日、英ロイター通信を介し世界を巡った。頭巾をかぶり、おしゃぶりを口元に寄せた遺体の写真を、例えばメキシコの新聞各紙は一面で報じた。だが、国民感情を気にしたのか、米国の主要紙は事件を報じながらも、写真を掲載しなかった。自爆テロなどで米兵に死に、米政府がしきりと「長期戦」を口にし始めた、まだ戦争も序盤と思われていた時期だった。
ヒッラ病院によると、2時間ほどのナダル空爆で46人の民間人が死亡した。
「病院の外で横たわっていると、カメラマンが来て時間をかけ子供たちを写していった。普通の市民も撮っていた。だけど、私らはまだそのヤコブの写真を見ていない。一体、どこにあるんだ。見せて欲しい。うちにはヤコブの写真だけがないんだ」
米関係者は戦後も一家を訪ねてはいない。
「俺は単純な男だ。補償なんて言わない。ただ、ブッシュ(米大統領)に会って聞いてやりたい。何でこんなことをしたんだと。ブッシュが私に直接謝り自分の金で補償するまで、絶対に許さない。何が勝利宣言だ」
奥で身を隠すようにしていた妻アリアさんが帰り際、姿を現した。「あなたの言葉を」夫を介し、そう頼み込むとアリアさんは両手を前に揃え、こんな風に言った。
「私たちには家具も何もない。だからみんな一番いい服に着替え一番いい靴をはいて、リュックサックに自分の物を詰めて、家を出たんです。ピクニックに行くみたいに」「私は魂を信じています。だから、今もみんなきっとジャナ(楽園)でピクニックをしているはずです。だって、あんなに喜んでいたんですもの」
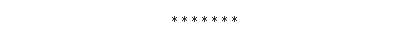
これには後日談がある。
後日、知人に送ってもらったロイター通信撮影のヤコブちゃんの写真をアブドゥルさんに届けた。
土間で写真を渡すと彼はヒッと音を立て息をのんだ。そしてしばらく荒い息を吐き続けると、「これは見せられない」と写真をあわてて戸棚に隠した。奥の間にいた妻アリアさんが気配を察し土間に姿を現した。そして夫に言い募った。「ねえ、どこ。この人、持ってきたんでしょ。ヤコブの写真はどこ」「そんなものはない」と脇を向く夫に妻は絶叫した。「どこ。写真、出してよ。どこよ。早く見せて、早く」
|