|
冷戦が終わり、諍いも隔たりもない世界が広がる。そんな風に考えたのもつかの間、人々は以前よりも内向きに、自らの殻、国家や民族に閉じこもり始めた。これは一時的な反動なのだろうか。それとも、こうした息苦しさはこれからも続くのか。人々が国家や民族、人種という鎧を剥ぎ取り、自分自身になれる時代はやってくるのか。ジャーナリスト藤原章生氏が、世界各地の現場から、さまざまな人間との出会い、対話を通して考察する。
 |
1999年、ヨハネスブルクの自宅で会見する
ナディン・ゴーデマさん |
とても大事なひとときだった。雨のヨハネスブルク。南アフリカのこの町に珍しく、朝から雨が降り続く午後のことだった。私は作家のナディン・ゴーディマさんから3時間ほど話を聞いた。彼女のやや上向きの賢そうな表情、しわの寄った細い手の動き、そして窓から入り込むまぶしいほどの芝生の緑。そんな情景とともに彼女の言葉のいくつかをはっきりと覚えている。
だが、その言葉は不思議と彼女がやや高い声で語る英語としてだけでなく、いくつかの表現は日本語として記憶されている。多分、テープおこしをしたときや実際に記事にまとめたときの翻訳作業を経ているからだろう。その日本語の言葉が追いかけてくる。
「本当にひどいものですよ。悲惨というのか。悲しいこと。自分の言葉を失ったということは本当に惨めです。自分たちはどこから来たのか。自分たちは何なのか。それを自分たちの言葉で語れない。その拠り所がないんですから。その点、アフリカ人は強い。どんなに酷い目にあっても、自分たちの言葉を捨てませんから。だからアフリカには、まだしも希望があるんです」
私はその時点で5年ほど暮らした南アフリカのことを、特にそこに暮らす人の普段考えていること、日々の悩みや暮らしぶりに関心を持っていた。地域性や時代が個人の考えや感覚にどのような影響をもたらすのか。彼らはどんな風に幸福や不幸を感じるのか。そこにこだわっていた。
南アフリカでは当然ながら人種問題が絡んでくる。長く続いたアパルトヘイト(人種隔離)も、一夜で消えるわけではない。「それでも少しずついい方向に向かっている」というゴーディマさんに米国の黒人について聞いたとき、「彼らは本当に可哀想」という言葉が出てきたのだ。
部族語など独自の言語を持たないことが米大陸に無理やり渡らされた黒人たちの不幸だと作家は言い切った。言い方があまりにきついので、「この人は米国の黒人との間で何かあったのでは」と疑ったほどだ。そして、内心、「この女性、自分がアフリカ生まれだからって、アフリカ人を持ち上げすぎてないか。本当に希望なんてあるのだろうか。米国嫌いが高じてこんなこと言ってるんじゃないか」と思ったりもした。
でも、あれから5年近くが過ぎ、米大陸の人々と接する中、作家の言葉の重さを感じるようになった。確かに米大陸の黒人はアフリカ人より深い不幸を抱えている気もする。でもそれは、いまだに差別の続く社会のせいとも言える。独自の言葉を持たないことが必ずしも不幸を生んでいるとは言えないのではないか。作家の言葉を全面的に支持できないのはそんな疑問からだ。
事実、内戦や暴力、飢餓の絶えないアフリカに比べ、仮に社会の底辺をうろつきまわろうと米大陸の黒人の生活の方がましに見える。それでも個人が抱く幸福や不幸の感覚がお金に左右されないことは、戦後を生きてきた日本人の多くが実感してきたことだ。大陸間の経済格差だけで不幸を計ることなど、できはしない。
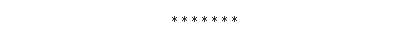
 |
1996年、ルワンダの首都
キガリで |
アフリカ大陸を東西に分かつ大地溝帯。その溝が狭まる高地の森にルワンダという国がある。ある晩、小さな民宿でこんなことがあった。そのとき、私は米国黒人の雑誌記者マーカスと、ルワンダ人の私の助手、モーリスと一緒だった。もともとそりが合わなかったのか、アフリカに来たばかりのマーカスはモーリスとちょっとした言い争いをした。些細なことだった。あたりで起きている虐殺について、性急な答を求めるマーカスと、物事はさほど単純ではないと主張するモーリスがぶつかったのだ。だが、いずれも30前後の若輩である。いさかいは、「俺が俺が」という無意味なボス争いに毛の生えたようなものだった。
「お前も同じ黒人なら少しはわかるだろ、アフリカのことが」
ゲリラ上がりのモーリスは締めくくりにそう言いきった。「米誌初の駐南アフリカ黒人特派員」という鳴り物入りで来たばかりのマーカスは「ふん」と鼻で笑い、「お前、腕見せてみろ」と右腕をテーブルに置いた。
モーリスの黒い腕とマーカスの褐色の腕が食後のテーブルに並んだ。
「見ろ。お前と俺は違うんだ。お前はアフリカ人、俺はアメリカ人。こんなに色が違うじゃないか」
「一緒にするな」ということだろうが、それにしてもあからさまなことを言う。マーカスはモーリスがよほど気に入らないのか、席を立つとひとり部屋に戻っていった。テーブルにはモーリスの腕が所在なげに残った。目を閉じ、頭を左右に静かに振るモーリスの仕草は「話にならない」という意味の一つのポーズだ。怒るとむしろ冷たい表情になる彼は傷ついたのだろうが、それはどちらかというと大した傷ではない。むしろ大半のアフリカ人が一度ならずと経験する程度のことだ。アフリカが米国など先進国と違うのは当然だし、その米国に住むかつての同胞たちに、彼らはさほどの思い入れがない。その同胞に「俺はお前たちとは違う」、もっと露骨に「君たちのように遅れてはいない」と言われても、さして響かない。
マーカスの方がもっとねじれている。彼は皮肉にも黒人のアフリカ回帰運動を進めたマーカス・ガーヴェイ(1887-1940年)から名づけられている。その彼は「アパルトヘイト後の黒人政権を黒人の目で報道する」という米国本社の視点で派遣された幾多の米国報道陣の一人である。
彼は色は黒くても、あるいは何代も前の先祖の一人が奴隷としてアフリカから渡ってきたとしても、あくまでも一米国人である。「アフリカ系」だからこそ与えられたポストだとしても、「アフリカ人をより理解できる」という期待に本当に応えられるのか。そんな疑問もあったのではないか。
確かに米国もつい最近まで、法的には60年代半ばまで事実上のアパルトヘイトがあり、マーカスの父母の世代はひどい差別にさらされてきた。被差別者なりのものの見方、考え方というものがあるのは確かだが、被差別者という立場はアフリカ人のさまざまな顔、性格のごく一面にすぎない。しかも、差別や人種問題はあくまでも欧州人が作り上げた欧州的なものであり、アフリカ人が生み出したものではない。それゆえ、被差別という一つの共通点で、この大陸に送り込まれ、「君ならアフリカがわかる」と勝手に思われているマーカスの苛立ちもわからないではない。
 |
1996年、ザイール(現コンゴ民主共和国)の
キクウィトで |
「あーあ、マクドナルドはないのかよ。チーズバーガー食いてえよ」。内戦が始まったコンゴに入り込もうとブルンジという国の国境で野宿したとき、マーカスは同じ不平を繰り返した。そして、国境警備に当たるブルンジ人とビールを飲んでいる私にも「お前、あんな教育のない連中と話して、どんな意味があるんだ」などと八つ当たりする。
彼の両親はアフリカ行きが決まった息子をどんな風に見送ったのか。「マーカス、お前、ついに帰るんだねえ」などと涙ぐんだのだろうか。そこまで漫画的な場面はなかったにしても、マーカスが多少の期待を抱いてこの大陸に来たのは確かだ。それでも「俺、やっぱアフリカ人じゃないね」と気づくのに1ヵ月とかからなかったろう。目の前にいるおかしな言葉を話す、他人とあまりまっすぐに目を合わせない、一見控えめに遠くから外国人を見据え、何かきっかけがあると猛スピードで混乱を引き起こすエネルギー、生命力のようなものを秘めた人々。その子供じみたような笑い方、それに、そもそも人々が放つ雰囲気、匂いが違う。マーカスが自分はアフリカ人ではないと思うのは当然のことだ。
「アフリカに帰ろう」と西アフリカやエチオピアに戻った米大陸の黒人は、ナイジェリアの沿岸など一部を除き、アフリカ社会に受け入れられず孤立した。そればかりでなく、彼らの到来はアフリカ人の側に差別や階級意識を広める結果にもなった。19世紀にアフリカに帰還した米国の黒人が築いた西アフリカのリベリアで、いまだに内戦が続くのも、西欧文明を見知った米国の黒人たちが生粋のアフリカ人を前に抱いた特権意識が根にある。時代は違っても、この大陸には幾多のマーカスが現れ、同じ苦悩を繰り返したのではないだろうか。
 |
| 1998年、西アフリカ、ギニアのボッファで |
では、アフリカ人はこうしたよそから来るアフリカの子孫をどう見ているのか。見方はさまざまだが、外見が明らかに違う白人や我々東洋人に対してよりも、より厳しい目で見ているところがある。例えば、同じチップを受け取るにしても、アフリカ系の男がアフリカ人に「ほらよ」と渡したりすると、「何であんな態度をされなきゃならないんだ」と腹を立てたりする。
クリントン夫妻がアフリカを歴訪した際、長年にわたる奴隷貿易の負の遺産に対し、米大統領として謝罪した。肯定的に受け止める人も多かったが、逆に「我々こそ謝罪しなくてはならない」などと言うアフリカ人も結構いた。つまり、奴隷貿易でもうけたのは英、仏、蘭、西、ポルトガルらの欧州人と、それを受け入れた米国やブラジルの主に特権層だが、それだけではない。貿易には多数のアフリカ人も協力している。特に強い部族や、部族の中でも貴族階級に属する者たちは支配下のアフリカ人を欧州人に売り渡した。アフリカは口コミの情報が驚くべき速さと正確さで伝わる社会だ。売られた奴隷がどのような末路を遂げたか、アフリカ人が知らなかったはずはない。それを承知で主に大西洋沿岸に住むアフリカ人自身が、西洋文明という基準から見てはるかに遅れた内陸に住む「未開のアフリカ人」を戦で捕らえ、売り渡したのだ。15世紀からポルトガル人と接触してきた沿岸の民と、19世紀に入りようやく欧州人を目にした内陸の民とでは、同じアフリカ人でも、相当な差がある。
だから、アフリカでも自分が主に特権層に属していたと考える人々は「謝るのは我々」という考えにいたる。その底には、米大陸の黒人を「我々自身が売り払った敗者たちの末裔」という見方がある。アフリカ人には新しいもの、新しい人々をすぐに受け入れない保守的な面がある。肌の色が近く似た骨格をしているというだけで、同じアフリカ人として受け入れる度量はないのだ。もちろん、17世紀に帰還した元奴隷を丁重に迎えたナイジェリアのヨルバ族など例外はいくつもあるが。
こうした人々を前にマーカスは傷つき、攻撃的になっていったのかもしれない。でもこの感覚はアフリカ人だけのものではない。例えば、スペイン、フランスなど父祖の地に戻っても決して欧州人と同じ扱いを受けず、逆に民族主義を膨らまし帰国した画家、ディエゴ・リベラをはじめとするメキシコ人たち。イスラエルを訪ねてみて、「やっぱり自分は南アフリカ人だ」あるいは「米国人だ」と主張し始めるユダヤ人たち。彼らも「ここは思い描いていたような自分の土地ではない」という落胆があったのだろう。
 |
2000年、南アフリカ北部
ベンダ族の村で |
南アフリカに生まれたある中国系の女性は客家(はっか)出身の自分のルーツを探り、100年以上におよぶ南アの中国人の歴史を編んだ。それからしばらくして、中国大陸を初めて旅した彼女は、言葉を抑えながらもこんな風に自分の気持ちを表現した。
「その雄大な景色、自然を見て、なんとも言えない感動を覚えた。自分の祖先の地に帰ったんだという気持ち。でも、そこにいる人々の振る舞い、顔つき、話し方を見ると、自分は明らかに違うんだと気づいたんです。列もつくらず列車に殺到する人やところ構わずわめいたり、唾を吐いたり。はっきり言って、ショックでした」
同じような言葉を日系人からも聞いた。アルゼンチン生まれのガブリエラは顔つきこそ日本人そのものだが、その開けっぴろげな振る舞いや仕草、自己主張の強い話し方から自身も言うように「イタリア系のアルゼンチン人」のようだ。スペイン人の夫と暮らす彼女はあるとき「あまり思い出したくないけど」と日本に留学したときの体験をこう語った。
「ホームステイのホストファミリーは神戸のお金持ちで、外国人を受け入れるのに慣れている風だった。でも、私を見たときに明らかに落胆していた。なぜって、私は金髪でも青い目でもないから。見たところ日本人と同じ顔だから。だけど私は日本語なんて全然話せないし、アルゼンチン人なわけじゃない。でも、彼女たちはそれを受け入れられない。白人の留学生をあちこち連れ回すのに、私は放っておかれた。私、めげない方なんだけど、やっぱり、何でだろうってずいぶん悩んだ。彼らの心のありようを探ろうと。でも、自分はこういう日本人とは明らかに違うなって気づいて、そういう人はとにかく無視しよう、この私を知ろうともせず、ほんとうに可哀想な人たちって思うようにしたら気が晴れた」
ガブリエラも、ナディン・ゴーディマさんに言わせれば「ルーツの言葉を失った不幸な民」の一人ということになる。客家の女性もそうだろう。世界に散在する大方の移民はそういうことになる。でも、果たして彼らは不幸なのか。そうとは言い切れないのではないか。でも、この答えをアフリカ系にも当てはめるには、米大陸にわたったアフリカ人の末裔たちにもう少し触れる必要がありそうだ。
(敬称略、つづく)
|