 |
ベリナ・ハス・ヒューストン
©Velina Avisa Hasu Houston Family Trust |
第5回に取り上げたフィリップ・ゴタンダと並んで、ベリナ・ハス・ヒューストンは、日系アメリカ人を代表する劇作家である。出版された作品数は、ゴタンダが8、ヒューストンが6、電子書籍を含めるとゴタンダが15で、ヒューストンが11である。この数字は、日系だけでなく、アジア系という枠組で見ても、かなり多い。
ヒューストンは父親がアフリカ・ネイティブアメリカン系、母親が日本人の戦争花嫁なので、3つの血が混ざった2世だ。戦争花嫁とは、米軍人と国際結婚し、戦後の1947年から60年代にかけて海外に移住した日本人女性のことで、アメリカに渡った戦争花嫁は5万人から10万人と言われている。
日本で上演された彼女の戯曲は、「Tea (ティー)」(1993、1995、1998、2009)と、「Calling Aphrodite(ヒロシマよ、アフロディテよ-女と影-)」(2008)である。作品が日本で上演された日系人劇作家は、彼女を除くと、フィリップ・ゴタンダ、ワカコ・ヤマウチ、リック・シオミの3人だけだ。「ティー」は、同じ劇団が4度やったのではなく、違う劇団がそれぞれの訳で上演したもので、この作品への関心の高さがうかがえる。
ゴタンダと同じく、ヒューストンには、自分の家族をテーマにした作品がいくつもある。代表例が、劇作家になって間もない1980年代に書かれた3つの戯曲である。まずは「Asa ga Kimashita(朝が来ました)」で母、セツコが黒人の血を引くアメリカの軍人と結婚し、日本を出るまでの経緯を描き、「American Dreams(アメリカン・ドリーム)」では、渡米後、セツコが白人社会からだけでなく、夫の家族からも差別を受ける様子を描いた。そして、3部作最後の「Tea(ティー)」で、夫を亡くした母と、他の4人の戦争花嫁の物語を重層的に描写した。
「ティー」はアメリカでも評価が高く、1985年にサンフランシスコで初演されて以来、60回ほど公演が行われている。彼女の作品はこの30年で30作以上が上演されているが、この数はダントツに多い。文字通り、彼女の代表作である。この作品を知るにはまず、彼女の両親の話から始めなくてはならない。
あらゆるコミュニティから差別された母の人生
 |
ベリナの両親。
1950年ごろの東京にて
©The Velina Avisa Hasu Houston Family Trust |
ベリナは1957年に、日本人の母、セツコ・タケチとアフリカ・ネイティブアメリカン系の父、レモ・ヒューストンとの間に生まれた。セツコは愛媛県松山出身で、商家の生まれだった。アラバマ州生まれのレモは12歳で両親を亡くし、その後ニューヨークに渡って軍人になった。セツコは外の世界を知りたいという欲求が強く、神戸でアメリカの進駐軍の通訳として働いていた母の従妹を訪れたことがきっかけでレモと知り合い、8年の交際を経て54年に結婚した。ベリナはアメリカに向かう船の中で生まれたが、父が軍務についていた日本が出生地として登録された。
一家はカンザス州のフォート・ライリー陸軍基地に隣接したジャンクション市に移住した。ここには戦後、日本人だけでなく、タイ人、韓国人、イギリス人、イタリア人、ドイツ人、フランス人など、米軍人と結婚した10万人ほどの戦争花嫁が暮らした。
セツコはアメリカに幻想をいだいていたが、現実の生活は厳しく、近隣の白人の家族からも黒人の家族からも差別を受けた。また、戦争花嫁は英語力も乏しく、日本の文化に固執する傾向が強いため、同化志向型の日系社会の中でも差別の対象となった。
 |
『写真花嫁・戦争花嫁のたどった道』 |
前回、このコラムで、日系社会における差別の問題を取り上げたが、戦争花嫁もまた、例外ではなかった。『写真花嫁・戦争花嫁のたどった道』(明石書店 2009)に収録されている「民間親善大使 アメリカの日本人戦争花嫁」で、ベリナは次のように述べている。
アジア系アメリカの歴史書から戦争花嫁の一団の移住についての記述は大きく削除され、ロサンゼルスにある全米日系人博物館でさえも、戦争花嫁の移住についての記録はまったく展示していない。(安富成良訳から一部改訳)
だが、戦争花嫁たちは、アメリカで辛抱強く生き、草の根レベルで日米間の関係改善に多大な貢献をした。たとえば、セツコは近くに住んでいたドイツ人の戦争花嫁と彼女の夫に巻寿司をご馳走し、その後、お互いの国について話をするようになった。戦争花嫁たちが民間親善大使だったことを、ベリナはこのエッセイで強調している。
アメリカ人とアジア人の親をもつ子どもとして
戦争花嫁の子どもであるベリナ自身も、様々な差別に遭遇している。沖縄出身の日系移民から「あなたのお母さんは売春婦だった」と言われたこと、学校での優秀な成績を学校側が認めたがらないことなど。アメリカは彼女を日本の子と見なし、日本はアメリカの子と見なす。でも、彼女は、そうした両方の存在であるがゆえに、アメリカの持つ独立心の感覚と日本人が持つ集団やコミュニティの感覚の両方をうまく融合することを学び、新しい考え方を創造している、と自分の立場をポジティブにとらえている。
サンフランシスコにあるアジア系アメリカ・メディアセンター(CAAM)が1993年に配給したドキュメンタリー作品、「Do 2 Halves Really Make a Whole?(半分2つを足して本当に全体になるのか)」で、出演者の1人であるベリナは、こんな話をしている。
よく思い出すことがあります。4歳のとき、ある日台所に行って、父に聞いたんです。「なぜパパはチョコレートで、ママはバニラなの?」。すると父は家を出て、お店でアイスクリームを買ってきました。父は、まず茶色のアイスクリームをスプーンですくって、これが黒人だった自分のお父さんだといいました。それからストロベリーを一すくいして、これがネイティブ・アメリカンだった自分のお母さん。その後バニラをすくって、これが日本人の君のお母さんだと。その後3つを混ぜて、これが君なんだよ。これをもとの3つにわけることができるかいって。もちろんできるわけがありませんが、これが自分のアイデンティティについての非常にわかりやすい父の教えでした。その教えは今でも生きています。
混ざったアイスクリームを分けることはできない。だから、彼女は、ジャパニーズ・アメリカンとかアジアン・アメリカン、アフロ・ジャパニーズといった2つに分けられる言葉よりも、アメラジアン(アメリカンとアジアンを足して一つにした言葉)という分けられない言葉で自分の存在を規定することを好んでいる。
歴史書から消された戦争花嫁を戯曲に
 |
『Unbroken Thread』 |
1985年に初演された戯曲「ティー」は、『Unbroken Thread』(1993)という戯曲集に台本が収められており、この本の表紙にはアメリカでの公演時の写真が使われている。写真に映っている5人は、カンザス州のジャンクション市に住む5人の戦争花嫁、ヒミコ、アツコ、セツコ、チズエ、テルコ。出身地も夫の人種も違う5人は、ヒューストンの母を含めて、彼女がジャンクション市で知り合った複数の戦争花嫁がモデルになっている。
主人公のヒミコは日本での不幸な生活を逃れるために、アメリカでアメリカ人との生活に賭けるが、その希望は夫の暴力で崩壊し、夫を射殺してしまう。さらに一人娘のエミコが強姦の後に殺されるという事件がおき、この後、ヒミコは自らの命をも絶ってしまう。
事件の後、アツコ、セツコ、チズエ、テルコの4人が、ヒミコの家に集まって、お茶を飲みながら自分たちの日本での境遇やアメリカでの生活について話をする。その会話にヒミコも亡霊として参加しているのが面白く、また各人が時に夫になったり自分たちの子どもになったりして心情を吐露している部分も興味深い。彼女たちの感情は時に激しくぶつかるが、徐々に連帯感を深めていく。
チズ:今日集まってよかった。どうしてかわからないけれど、日本の女の人と一緒にいると心が休まる。
セツコ:助けたいと思っていた人を皆呼べばよかったわね。今日、お茶を飲むだけでも違う。
アツコ:ええ、お茶の味も違うし。
チズ:また、お茶を飲もうか。みんなで。
セツコ:そうね、近いうちに。
そして、亡くなったヒミコをお茶に誘うところで幕が下りる。お茶は、アメリカに住む日本人にとって、あるいは作者にとって、心を癒してくれるものの象徴なのだろう。ヒューストンは緑茶を表すgreenteaを自分のメールアドレスに使っているほど、お茶に対する思い入れが強い。
戦争が世界にもたらすものを見つめる
 |
練馬区「ブレヒトの芝居小屋」での2008年公演のチラシ |
日本人とアメリカ軍人との間に生まれたヒューストンにとって、戦争は、人種と同様、大きなテーマである。2007年に、戦争をテーマにした「ヒロシマよ、アフロディテよ―女と影―」が、ロサンゼルスで初演され、昨年(2008年)の8月には日本でも、練馬区にある「ブレヒトの芝居小屋」でリーディングの形での翻訳版が上演された。
1955年5月、被爆した25人の女性たちが、ケロイド治療のために渡米し、1年半の間に計138回の形成手術が施された。「ヒロシマよ、アフロディテよ」は、原爆乙女(Hiroshima Maiden)と呼ばれる彼女たちから着想を得て書かれた作品である。
物語はケイコ・キムラとシズコ・キムラという姉妹を中心に展開する。姉のケイコはプライドの高い欧米志向の美人で、意中の男性もいた。一方シズコのほうは生真面目で器量もそれほどでなく、いつも姉の陰にいるような存在だった。
そんな2人が広島の原爆で被爆する。ケイコは髪が焼け落ち、頭皮が損傷し、着ていた白い着物の色柄が皮膚に食い込んでいた。ハンセン病患者のように扱われる中で、教会だけが2人を人間として扱ってくれた。そして被爆後10年間、2人は教会の地下で暮らし、孤児たちにボランティアをしていた。
シズコはキリスト教という信仰を得て、生きる希望を見出したが、美しさを失ったケイコは人生に希望を見出せず、アメリカに行って手術を受けたらどうかという医師の誘いにも同意しかねていた。
シズコに説得されて、2人はニューヨークに行くことなる。だが、治療を担当したエバレット医師は、麻酔薬の投与ミスでシズコを死なせてしまう。失意の中にいるケイコに、医師はグアム島で自分の弟が日本の兵士によって殺されたことを話す。医師はさらにこう続ける。
エバレット:戦争がもたらしたものは、あなたの怒りや私の怒りで消えるものではない。罪の意識でも消えはしない。私たちのいくつかの断片は永遠に失われるが、残った部分で、この宇宙のなかでバランスをとれないものだろうか。私はその機会を求めたいし、許していただきたい。それがあなたの妹さんが望んだことでもないだろうか。
アフロディテはギリシャ神話に出てくる愛と美の女神だが、一種の狂言回しのように戯曲のところどころに現れて、美と愛についてケイコと語り合っている。
ヒューストンはこの作品で、アメリカの原爆投下の是非については一切語っていない。戦争を未然に防ぐべきだとも言っていない。彼女が語るのは、戦争が起きてしまった場合の、その後の人の心の在りようだ。
この作品は2007年の8月から9月にかけてロサンゼルスで初演されたが、そのときのプログラムにヒューストンは次のように書いている。
この作品は第2次大戦についての話であるだけでなく、現在、未来の戦争と、それが世界にもたらすことについて書いたものです。もし私たちが戦争を止められないのなら、そのあとどうしたらよいかを知ることが大切です。(中略)戦争のあとには、国を立て直し、人間の心を回復させるために、さまざまなかたちの美が必要です。広島原爆乙女計画は、戦争の傷跡を癒すための核戦争後の重要な博愛主義的努力の中で、日本とアメリカという2つの敵対しあっていた国を結ぶ親善事業の一つでした。この事業は私たち人間に希望と勇気を与えてくれるはずです。
多文化、多人種の劇作家として
ヒューストンは子どもの頃から文章を書く才があり、高校生の時に書いた詩がカンザス州の賞を獲得している。カンザス州立大学でジャーナリズムの学位を得た後ロサンゼルスに移り、1981年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で戯曲「Asa ga Kimashita」を書いて修士号を取得。その後、南カリフォルニア大学の映画学科で博士号を取り、現在は同大学の演劇学部で演劇論を講じている。また、1990年には学内で脚本部門の大学院を立ち上げ、創作の指導をしている。
劇作家としての活躍は目覚しく、冒頭にも書いたが、30以上の戯曲がアジア系、アフリカ系、その他の劇場で上演されている。彼女の作品は、内容がアジア系とアフリカ系の両方に跨る場合が多いため、アジア系の劇場で上演するにはアジア系の要素が足りず、アフリカ系の劇場にかけるにはその傾向が弱いと上演を敬遠され、皮肉にもヨーロッパ・アメリカ系の劇場や演出家に迎えられることがある。実際、代表作の「ティー」は、有色系の劇場よりも、ヨーロッパ・アメリカ系の劇場での公演のほうが多い。
この状況を、彼女は「有色同士の抑圧」と呼んでいる。イースト・ウエスト・プレーヤーズ(EWP)など、アジア系の劇場は、元来、白人社会から受ける差別への抵抗として生まれた経緯がある。差別をなくすための演劇活動が、自分たちの民族性にこだわるあまり、他の民族を排除してしまう。最近では、そういったある種の"縛り"をかけないアジア系の劇場もあるが、最終的には民族を超えた活動を行っていくべきだと私は思う。
未来の劇作家を育てるために
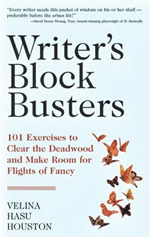 |
『Writer's Block Busters』 |
ヒューストンは創作のクラスでどのように教えているのだろうか。また、自らどのように作劇しているのだろうか。アイデアは次々と生まれてきて枯渇することはない、と彼女は言い切る。そのアイデアはどこから生まれてくるのだろうか。そのヒントが、昨年(2008年)出版された『Writer's Block Busters』という本にある。副題が、「無駄なものを除いて、空想の旅にでる101の練習」。
前書きで、創作は教えられるものではない、ときっぱりと言い放ったうえで、劇作家を目指す学生にどんなアドバイスをしているかを述べている。たとえば、読書をしたら、それについて書き手の視点から話すようにすること、ある戯曲を書くにあたり、なぜそれが重要かを考えること、など。本編では、この20年間、教員として学生に与えてきた具体的な課題が示されている。
とはいえ、彼女は、技術論よりは個々の学生が持っている内なる声を発展させていくことを第一に考えている。また、時々学生を外に連れて地理を把握させ、異なった環境で書かせることもしているという。
小説家としての第一歩
私は10年ほど前に、ロサンゼルスでヒューストンと息子のキヨシ君に会い、チャイナタウンで中華料理を突っつきながらいろいろ話をした。その時、彼女は「ティー」を小説にしたいと言っていた。読者を幅広く獲得するにはやはり小説だ、という思いが彼女のなかにあるのだろう。戯曲とは作法が違うので難しい、とその時は話していたが、最近のメールで、小説版はすでにてきているので、日本語版を出したいということだった。
これは是非実現してほしいが、同時に映画化も期待したいと私は思っている。 ※本文中に引用した翻訳は、但し書きがあるものを除いて筆者による。
|