|
「ウェンブレイの雪辱」を果たした興奮
 |
メキシコW杯の対イングランド戦
西ドイツの決勝点を紹介するページ
Fußball Weltmeisterschaft Mexico 1970
©1970 by Wilhelm Limpert Verlag |
「すばらしい! 信じられない! 奇跡的だ! こんなことってない!」
フランスのスポーツ紙『レキップ』は、メキシコ・ワールドカップ(W杯)準々決勝のイングランドと西ドイツの熱戦をこんな見出しで伝えた。勝利の瞬間、あちこちで大騒ぎが起こっていた。コマンチラのドイツチームの宿舎の厨房では、シェフのゲオルク・ダムカーが、インディオのお手伝いの女性達から手荒な祝福を受け、床に押し倒された。遠く離れた故国ドイツでは、ヘルムート・シェーンの夫人アンネリーゼに、知人の女性が電話口で叫んだ。
「勝ったわ! 勝ったわ!」
テレビの解説をしていた英国人ジョー・マーサーは、面白いコメントを残している。彼は当時のイングランド1部リーグ(現在のプレミアリーグに相当)でもトップクラスにあったマンチェスター・シティの監督を務めており、名指導者として知られた人物である。
「ヘルムート・シェーンは、アルフ・ラムゼーとの戦いに勝った。この試合は11人対11人ではなく、控え選手2名と監督を含めた14人対14人のゲームだった。戦術面で、ラムゼーはシェーンに敗れた。シェーンは、シュルツとグラボフスキを入れることでイングランドのハーストとクーパーの動きを封じた。逆にチャールトンを交代させたラムゼーは、ベッケンバウアーを止められなかった」
この大会から認められた選手交代の新規則を、シェーンはうまく利用したことになる。
かくして、1966年W杯の「ウェンブレイの雪辱」は成り、ドイツは2大会連続でW杯のベスト4に進出した。スタジアムでの記者会見を終え宿舎にもどると、選手たちはすでに隣接するプールでくつろいでいた。マックス・ローレンツとホルスト・ヘッティゲスが、まじめな顔で近寄ってきた。
「時計をはずしていただけますか?」
シェーンは言われるとおりにした。
「さあ、あなたの番ですよ!」
2人は、服を着たままのシェーンをいきなり水の中に投げ込んだ。心地よい満足感が心に広がっていった。
準決勝の組み合わせは、西ドイツVS.イタリア、ブラジルVS.ウルグアイとなった。4チームともW杯優勝経験国である。優勝チームに贈られる「黄金の女神像ジュール・リメ杯」は、規定で3度チャンピオンになった国が永久保持できる。4チームの中でドイツだけが1度の優勝。あとの3ヵ国は、いずれも2度の優勝を果たしており、この大会で女神像を永遠に祖国にもちかえる可能性がある。
西ドイツ対イタリアの試合は、メキシコ・シティのアステカ・スタジアムで行われることが決まり、シェーンたちはメキシコ・シティからバスで2時間ほどかかるプエブラ市を新たな本拠地とした。市内の喧騒の中に身を置くよりは、郊外のほうがゆっくり過ごせるという配慮からである。
チームは4週間を過ごし、住み慣れたコマンチラを去ることになった。周囲にこれといった娯楽施設がないため、退屈なのが玉にキズだったが、設備は非のうちどころがなく、思い出の多い宿舎であった。ゲルト・ミュラーとウーヴェ・ゼーラーを同室にしたのもよかった。大会前に心配された2人の併用は功を奏し、ピッチ外でも互いの理解を深め合っていた。
地元の住民とも良好な関係を築くことができた。別れに際し、ドイツチームは警備を担当してくれた人々に、感謝の気持ちをこめて母国からもちこんださまざまな品を贈った。「いっぱいの荷物をもって到着し、帰るときはほとんど何もなかった」とはミュラーの感想である。
鉄壁の守備システム、イタリアの「カテナチオ」
古来、ドイツ人はイタリアに憧れている。大文豪ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテは謳った。「きみ知るや、レモンの花咲く国・・・」
ある年の9月、日によっては、すでに肌寒さを感じるドイツの秋であった。ドイツ人の恩師の案内で南ドイツ−北イタリア間を日帰りしたことがある。ミュンヘン郊外の恩師宅を早朝に車で出発。オーストリアを通り抜け、アルプスを越えて昼前には北イタリアに入った。第二次大戦前はオーストリア領だった南チロルと呼ばれる地方である。山を越えて驚いた。まるで日本の初夏のようだった。針葉樹の多い単調なドイツの森とは打って変わり、明るい太陽のもと、花や木々のこまやかな色彩がキラキラ輝いている。ヨーロッパの北と南、秋と初夏を同時に体験した。北部でさえ、この豊かな彩りである。南はさらに暖かいのであろう。ドイツ人がなぜイタリアを好むのか、わかるような気がした。
 |
| イタリア・ナショナルチームのマーク |
1950年代後半から60年代前半、サッカーの世界でも、イタリアはドイツの選手にとって夢の国であった。ドイツにまだプロ制度がない時代、イタリアの強豪クラブは、その豊富な資金力で海外からの有望選手を集めていた。ドイツからもアウグスブルクのヘルムート・ハラーや、ケルンのカール・ハインツ・シュネリンガーといった若手の代表選手が、イタリアのチームに移籍していった。1963年のブンデスリーガ創設により、ドイツでもようやくプロの時代が始まったとはいえ、年俸面ではイタリアのサッカー選手とは比べものにならなかった。
当時のイタリアサッカーを支配していたシステムが、安全第一の守備作戦「カテナチオ」である。「カギをかける」という意味のこのシステムは、4人の守備者の後ろに、さらにスィーパーを1人置き、中盤選手は3名ないし4名で構成する。ゴールキーパーをのぞく10名のうち、これら8〜9人に守備の意識を徹底させ、攻撃は1人か2人のフォワード選手でカウンターを仕掛けるというものである。あまりに守備的で悪名高いシステムだったが、効果は絶大だった。1960年代は、このカテナチオを旗印としたイタリアのチームが、クラブ対抗のヨーロッパカップ戦を席巻した。
このシステムの発案者は、一説にはトリエステ出身のネレオ・ロッコだと言われている。ロッコは、第二次大戦が終わった直後のイタリアサッカー界で、弱小ともいえるパドゥアを率いていた。彼は、すでに全盛を過ぎた選手や他のチームであまり評価されていない選手を集めてチームを作っていった。
1948年ロンドンで第14回オリンピックが行われた。今になってふりかえれば、戦争の被害の大きかった町で、よくオリンピックのような世界的なスポーツ大会ができたものだと感心する。サッカー競技ではスウェーデンが優勝した。中立国として戦禍を免れた国には、それなりの利があったのだろう。
同じ年、イタリア・サッカー協会は、外国人選手の受け入れを許可した。これを受けて迅速に動いたのはACミランである。スウェーデン金メダルの立役者であるグンナー・グレン、グンナー・ノルダール、ニルス・リードホルムの3選手と契約を交わした。名前の頭文字を取って「グレ・ノ・リ」と呼ばれた北欧の名手3人組の加入により、ACミランは一気に強力チームとなった。1951年にはイタリアチャンピオンに輝いている。当時のロッコ率いるパドゥアのような弱小チームが、有力外国人選手のいるACミランのような強豪と対等に渡り合うには守備を固めるのが一番だ。カテナチオはこうして誕生し、一気にイタリア全土に広がっていった。
ロッコは後にACミランの監督として招かれ、1967年イタリア・カップ(コパ・イタリア)、1968年イタリア・リーグ(セリエA)、ヨーロッパ・カップウィナーズ・カップ、1969年欧州チャンピオンズカップ、世界クラブカップと次々に優勝を果たした。
イタリアサッカー界には、もう1人、このカテナチオを掲げてヨーロッパを制覇した人物がいる。アルゼンチン出身のエレニオ・エレラ。インテル・ミラノを鍛え、1963年、65年、66年とセリエA優勝。1964年、65年には欧州チャンピオンズカップ、世界クラブカップともに連覇を成し遂げた名物監督である。「点を取られなければ、負けない!」という持論から、超守備的な戦術に走った。カテナチオは彼の発案という説もある。いずれにせよ、あまりに守り一辺倒の作戦は「サッカーの墓場」とも揶揄され、評判はよくなかった。
レアル・マドリッドの伝説の名選手アルフレッド・ディ・ステファノは、インテルの試合ぶりを、いみじくもこう評した。
「インテルは、ゴールキーパー1人と、10人の守備者のチームである!」
一方、W杯でのイタリア代表チームは、1934年、38年と2連覇したものの、それ以降はこれといった成績をおさめていなかった。特に前回の1966年大会では、ノーマークの北朝鮮を相手に0対1と、まさかの敗戦を喫し1次リーグで姿を消している。帰国したチームは、飛行場で待ち受けるファンから轟々の非難を浴び、トマトを投げつけられる始末であった。1970年大会は、意地にかけても名誉挽回に燃えるところである。
1次リーグは、3試合で得点1、失点0の1勝2引き分け。カテナチオ戦法で手堅く勝ち上がった。準々決勝では、一気にその実力を発揮し、地元メキシコ相手に4点を奪い圧勝した。
ロスタイムに入った同点ゴール!
1970年6月17日。空は曇りで、寒暖計は18度をさしていたが、暑かったという。
スタジアムのアナウンスがドイツの出場選手を伝えるたびに歓声が巻き起こった。ベッケンバウアー、オヴェラート、ゼーラー、ミュラーのときはひときわ高い大歓声になった。
つづいてイタリアのメンバーが発表された。非難の口笛が耳をつんざく。準々決勝で地元メキシコを破ったイタリアは、イングランドに代わる新たな敵役である。
試合開始直後は、ピンポンのように両チームのゴール前を交互に攻め合う展開であった。
8分、ドイツのベルティ・フォクツのパスがイタリアのフォワード、ボニンセーニャに渡ってしまい、1点を先取された。ドイツはフランツ・ベッケンバウアーをコントロールタワーとして反撃に出る。
この試合は、ドイツチームとそのファンにとっては、納得のいかない判定がつづいた。ベッケンバウアー、ゼーラー、フォクツが次々と倒されるが、笛は鳴らない。シェーンによれば、2度ペナルティキックを得ても不思議ではない場面があったという。
主審は日系ペルー人でメキシコ国籍のアルトゥール・ヤマサキであった。彼の勤務先の上司がイタリア系であったことから、後にそのジャッジについてドイツ側から非難を浴びた。そうでなくてもイタリアの守備は厳しい。ミュラーはこう語っている。
「イングランドは激しいがフェアだ。イタリアは必ずしもフェアとはかぎらない」
象徴的なシーンが65分におとずれた。ベッケンバウアーが、ドリブルでイタリア陣に突進する。ペナルティエリアのギリギリのところでイタリアのチェラがつぶしにかかる。長身のベッケンバウアーは大きな弧を描くように倒れた。主審はエリア外でのフリーキックを宣告。ドイツ選手がペナルティキックを主張し、抗議にかけよるがジャッジはくつがえらない。このチャンスも得点には結びつかなかった。
52分と66分、シェーンはラインハルト・リブダ、ズィギィ・ヘルトと2人のウィング選手をたてつづけに投入した。両翼からセンタリングを上げ、真ん中のミュラーとゼーラーで勝負するという作戦である。先発で出場していたユルゲン・グラボフスキも含め、3人のウィング、2人のセンターフォワードという非常に攻撃的な布陣となった。
転倒で痛めたベッケンバウアーの右肩の状態は、だんだんひどくなっていく。2005年9月、60歳の誕生日を迎えたベッケンバウアーの特集番組がドイツで放映された。このイタリア戦でのファウルをめぐって、彼は笑いながらこう言った。
「あの時は、ちょっと派手に跳びすぎたよ」
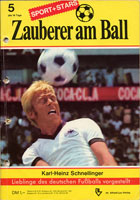 |
シュネリンガーが特集された雑誌
Zauberer am Ball
©1972 by Alfred-Lau-Verlag |
すでに2人の交代枠を使い果たしていたドイツは、ベッケンバウアーを代えることができない。もっとも、チームのキープレーヤーを失うことは致命的でもある。準々決勝で、1点リードしていたイングランドが、次の試合にそなえてチームの頭脳ボビー・チャールトンを温存するために交代させ、ドイツに逆転負けを喫したのは良い例である。ましてや、この時点でのドイツは、イタリアにリードされている。ベッケンバウアーは、歯を食いしばって耐えた。
ミュラーが虎視眈々と狙うが、イタリアの守備は堅い。イタリアゴール前には、まったく穴が見つからない。時は過ぎ、イタリアの時間稼ぎが始まる。90分。主審ヤマサキは、ロスタイムを取った。ドイツは総攻撃に出る。長身の守備選手カール・ハインツ・シュネリンガーが前線に上がってきていた。彼は、ドイツ人でありながら、イタリアのACミランに所属する選手である。シュネリンガーの上がりを見て取ったグラボフスキが、左からゴール前にセンタリング。シュネリンガーが伸ばした足がボールにピタリと合い、イタリアのネットを揺らした。ドイツは試合終了直前で同点に追いついた。
47回ドイツ代表を務めたベテラン、シュネリンガーの代表での得点は、この1点だけである。あまりにも貴重なゴールだった。
両者合わせて5得点、追いつ追われつの延長戦
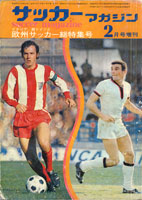 |
『サッカーマガジン1972年2月号増刊』(注)
(ベースボール・マガジン社) |
準々決勝のイングランド戦につづき、またも15分ハーフの延長に入った。ベッケンバウアーは右肩をバンデージで固定しての奮闘である。
「腕を固定されたので、体の動きまで制限された。100をベストとすれば、40か50の出来だった」
ここから「アステカのスリラー」と呼ばれた攻防が展開されていく。まず延長5分。リブダの右コーナーキックをゼーラーがヘディング。ゴール前にフワリと上がったボールを、イタリアの守備者とキーパーがさばこうとするその間に割って入ったのがミュラーだった。もつれこむような状態からミュラーの足に触れたボールは、スローモーションのようにコロコロところがり、ゴールラインを越えて止まった。ドイツが2対1とリードした。
その2分後、今度はイタリアのフリーキックからブルグニッチが決め2対2。フォワード選手でありながら、守備にもどっていたドイツ、ヘルトのクリアミスである。
さらに延長前半の終了直前、「イタリアの太陽」と呼ばれた強烈なゴールゲッター、ルイジ・リーヴァが、シュネリンガーをうまくかわしてゴールを決め、再び1点のリードを奪った。
延長後半、右コーナーキックを得たドイツは、グラボフスキが近寄ってきたリブダにパス。リブダのセンタリングからゼーラーのヘディング。跳ねたボールに向かってミュラーがくらいつくように飛び込み、頭でゴールに流し込んだ。試合はまた振り出しにもどった。
その1分後、イタリアの逆襲が始まった。速攻で左からボニンセーニャがもちこみ、ドイツゴール前におりかえす。ゴロのパスが真ん中から走りよったジャンニ・リヴェラに渡った。チームの頭脳としてコンピューターのように正確なパスを出すため「超頭脳」とあだ名されたこのACミランの名手は、そのままボールをゴールに流し込んだ。4対3。またもやイタリアがリード。イタリアの選手たちは、抱き合って喜びを表現する。対照的に、リヴェラをマークしきれなかったベッケンバウアーの姿が痛々しい。残り数分、ドイツは最後まであきらめずに猛攻を仕掛ける。しかし堅守で知られるイタリアは持ちこたえた。やがて、ヤマサキ主審の笛が鳴った。
試合は終わった。延長戦の30分だけで、両チーム合わせ5点が入るという大接戦だった。消耗しながらもボールを追う選手たちの姿は、世界中のサッカーファンに感動を与え、W杯屈指の名勝負となった。醒めたコメンテーターは「十年に一度のゲーム」と伝え、熱烈な批評家は「世紀の一戦」と呼んだ。
記者会見にのぞんだシェーンは、世界中から集まった200人もの記者たちから拍手で迎えられた。シェーンは、自チームへの誇りを短いことばの中に表現した。
「選手たちは、イングランドとイタリアという強豪を相手に、4日間で4時間(延長を含め240分)ものすばらしい戦いをした。この2試合を再現できるようなチームがあれば、教えていただきたい」
その夜は沈んでいたチーム内にも、翌日には、すでに楽天的な雰囲気がもどってきた。主将のゼーラーは語った。
「3位を目指して、全力で戦う」
3位ドイツへの称賛の声
準決勝のもう一試合は、3対1でブラジルがウルグアイをくだし、決勝に駒を進めていた。これで、ドイツは決勝戦の前日にウルグアイとの3位決定戦にのぞむことになった。
1970年6月20日。ベッケンバウアー、ヘッティゲス、グラボフスキの3名が負傷欠場したドイツチームは、それまでとは打って変わったメンバー構成になった。それでも、前半27分、リブダのセンタリングをゼーラー、ミュラーとつなぎ、中盤から駆け上がったヴォルフガング・オヴェラートが強烈なシュートをたたきこんだ。これが決勝点となり、3位が決まった。
後半からシュネリンガーに代わって、ひょうきん者のマックス・ローレンツが守備に入った。「控え選手の主将」はついにW杯の試合に出場を果たした。
イタリアとブラジルの対決となった決勝戦は、ペレのヘディングによるゴールを皮切りに、4点をあげたブラジルの勝利に終わった。ブラジルは通算3度目のW杯優勝となり、黄金の女神像ジュール・リメ杯を永久に保持することとなった。
 |
| ゲルト・ミュラーと筆者、1995年 |
初めての高地での開催が懸念されたメキシコ大会は、1人の退場者も出ないフェアですばらしいW杯となった。3位に終わったものの、W杯の歴史に残る熱戦をくりひろげた西ドイツは、「優勝したブラジルと戦わせてみたかったチーム」と各方面から絶賛され、10ゴールをあげたゲルト・ミュラーは得点王の座も手中にした。2005年11月、60歳の誕生日を目前にしたミュラーに、ドイツのスポーツ専門誌『キッカー』が、特別インタビューを行った。「(サッカー)人生で最良の時は?」との問いに、ミュラーは「1970年メキシコの4週間」と答えている。それほど印象的な大会であったのだろう。
祖国に帰る機内でシェーンは、満足気にこう語った。
「イングランド戦のタイムアップの笛が、いちばん印象に残っている」
前回の1966年につづき、国内では世界チャンピオンになったかのような歓迎を受けた。
シェーン夫人アンネリーゼにとっては、メキシコからの飛行機がフランクフルト空港の滑走路にすべりこんだ時が、もっともすばらしい瞬間であったという。ゼーラーとミュラーのポジションをめぐる大会前からの騒動、胃腸に持病をかかえたシェーンの健康状態、すべてを知っている夫人にとっては、夫がどんなに消耗しているかは十分に想像できた。出発前には、夫妻で「メキシコ大会が思うようにいかなかったら、どうなるかも考えなくては」と話し合っていたという。場合によってはクビになる可能性もあった。そんな心配を、好結果が吹き飛ばしてくれたのである。
いよいよ自国開催の1974年W杯をにらみながら準備を開始できる。その前哨戦ともいうべき1972年ヨーロッパ選手権が目前に迫っていた。
(敬称略、つづく) |