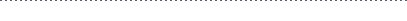
新書の歴史は1938年、岩波新書の創刊で幕を開けた。きっかけになったのは当時、岩波書店の編集者であった吉野源三郎(注1)が丸善の棚で見つけたペリカン・ブックスというペーパーバックスだったという。
ペリカン・ブックスとは、ペーパーバックスの代表的な存在であるペンギン・ブックスの版元から1937年に創刊された、一般教養書を中心とするシリーズである。
「値段もころあいだし、型がスマートでハンディーだし、分量も読み切るのに手頃で、書目も哲学、歴史、考古学、自然科学など多方面にわたって、かつ専門家でない読者にも興味の深いものが揃っている」(『岩波新書の50年』岩波書店編集部編、岩波新書)
この形式ならば、俗流に陥らないで多数の読者をつかめるのではないか。そう吉野は考えたのである。
もう一つの背景としては、国粋主義思想への抵抗があった。岩波新書創刊の計画が始まった1937年は盧溝橋事件から日中戦争が勃発し、翌年には国家総動員法が施行された。激しい言論弾圧が行われた時代にもかかわらず、岩波書店の創業者、岩波茂雄は岩波新書刊行の辞において
「吾人は非常時に於ける挙国一致国民総動員の現状に少なからぬ不安を抱く者である」
と勇気をもって書いている。
最初に刊行されたのは20巻。すぐに増刷になるほど反響は好調だったという。
記念すべき第1巻と2巻はデュガルド・クリスティーの『奉天三十年』上下巻だった。同書は1883年から1922年まで満州に伝道医師として献身的に活動し、現地で信望を集めていたスコットランド人クリスティーの回想記である。これには、大陸で力による征服を推し進める軍部に対し、クリスティーの「無私の奉仕」で無言の抗議をするとの含みがあった。なお、訳者は前年に思想的理由で東京帝大から辞職に追い込まれた矢内原忠雄である。
また、創刊20点の中には川端康成、横光利一、山本有三らの著作が含まれている点も注目される。歴史の最初から、新書は何でもありの世界だったのだ。
岩波新書は1938年に23点、翌39年に31点、40年に24点が出版された。武者小路実篤『人生論』や三木清『哲学入門』などが好調な売上を示したほか、斉藤茂吉『万葉秀歌』(上下巻)は今なお一般書店の本棚で手に取ることができる。
ところが、41年に入ると発行点数はわずか6点に落ち込む。戦時下で日本出版会という統制団体の認定によって印刷用紙が割り当てられるようになった結果、当局の意に沿わない出版物には意図的に用紙が手当てされなくなったためである。
以降、岩波新書の発行点数は42年が11点、43年1点、44年2点、46年3点(45年は刊行なし)となり、実質的な休刊に追いやられた。
岩波新書が赤から青にカバーの色を変え、「青版」として再出発を図ったのは戦後の1949年になってからのことである。
「新書」とは特に厳密な定義があるわけではなく、版型はB6版よりやや小型のサイズで、各社によって微妙に差がある。手元の岩波新書を採寸してみると縦17.3cm、横10.5cm。
一般には、こうしたハンディーな形態でかつ軽装、そして比較的安価な価格設定とシリーズで刊行されるといった要素が新書のイメージを形作っている。また、同じくシリーズで刊行されている文庫が主に既刊本を収録しているのに対し、新書は書き下ろしがメインという違いもある。
新書という言葉が広がったのは1950年代に入り、岩波書店が確立したこのフォーマットに他社が追随し始め、新書ブームと呼ばれる状況が生まれてからだろう。
1950年の角川新書、51年の文庫クセジュ(白水社)、52年の三笠新書等々、この時期に多くの新書が各社から創刊されている。ハードカバーの単行本として発売していた伊藤整『女性に関する十二章』の廉価版を、中央公論社(現中央公論新社)が新書版として改めて発行するとベストセラー化した。当時、軽装版・新書版のシリーズは93種類あったと言われている。
岩波新書が先駆けた「教養新書」に対し、54年に光文社から創刊されたカッパ・ブックスは「創作出版」をスローガンに掲げ、時流に合った企画と平易な文章、積極的な広告宣伝によって「実用・娯楽新書」というマーケットを創出。61年に発売した岩田一男の『英語に強くなる本』が発売2ヶ月半で100万部を突破したのをはじめ、多湖輝『頭の体操』、塩月弥栄子『冠婚葬祭入門』などが100万部を超えるベストセラーになった。
60年代に入ると、再び新書ブームと呼ばれる時代が到来する。62年に中公新書、64年に講談社現代新書が創刊され、後に教養新書の「御三家」と言われる3シリーズが出揃い、「教養」を求める読者に浸透していったのだ。
だが、60年代後半から70年代に入ると教養新書の売れ行きは鈍り出した。部数的には76年の渡部昇一『知的生活の方法』(講談社現代新書)が目立つぐらい。これまでの主要な購買層だった学生の読書傾向の変化がその原因と言われている。新書の低迷とは裏腹に、70年代は各社から文庫シリーズが続々登場し、読者の人気を集めていった。
教養新書が再び元気を取り戻すには、90年代まで待たなければならない。
88年、岩波新書は創刊50年を機に「新赤版」として新たにスタート。従来の版とは異なり、行間を広くとり、ひらがなを多用するなど読みやすさを重視した編集を行ったのが特徴である。
企画面でも従来の学問的、ジャーナリスティック的なものに加え、エッセイなどの軽い読み物まで守備範囲が広げられた。94年に発行され大ベストセラーになった永六輔の『大往生』や、水木しげる『妖怪画談』などがその系統に当たり、それまでの岩波新書のイメージを大きく覆し、新たな読者を獲得する役割を果たした。
一方、中公新書も92年に本川達雄の『ゾウの時間ネズミの時間』や94年に野口悠紀雄『「超」整理法』といったヒット作を世に送り出している。
こうした新書マーケットの盛り上がりを受けて、またまた出版各社の新書参入ブームが始まったのは必然というべきか。
主なところでは94年ちくま新書、96年KAWADE夢新書、PHP新書、98年文春新書と続いた後、99年には平凡社新書、宝島社新書(注2)、集英社新書と一気に三社が参入。また、講談社プラスα新書、中公ラクレ、岩波アクティブ新書など、すでに新書シリーズを持つ版元からも、従来とは別枠の新シリーズが創刊されたのも目を引く。
とりわけインパクトが大きかったのは、2003年創刊という後発ながら、養老孟司『バカの壁』が350万部を超える部数を記録した新潮新書だろう。その編集方針などについては、編集長インタビューが掲載されているのでご覧いただきたい。
20世紀の最後から21世紀にかけて、これほど新書が創刊された大きな要因の一つには、バブル崩壊以降の経済情勢がある。つまり、デフレ経済における消費者の低価格志向に対応し、多くの出版社が700~800円と手頃な価格の新書出版に走ったというわけだ。
実際、『出版指標年報』(2004年、全国出版協会出版科学研究所)の統計によると、1993年の新書本平均価格が739円なのに対し、2003年は771円と32円のアップにとどまっている。同じくペーパーバックスの文庫本は503円から604円と101円上昇しており、これと比較すると、新書の価格は極力抑えられてきたといえよう。
一方、同統計の新刊点数の項目を見ると、新書本は93年に2589点だったものが、95年から2000年を除き毎年3000点を超える新刊が発行され、ピークの02年には3510点、03年には3378点出版されている。
ところが、推定発行部数を見ると、93年が4654万冊だったのに対し、02年は4892万冊。03年には4475万冊と10年前よりむしろ減少。一点当たりの発行部数は減少する傾向にあるようだ。
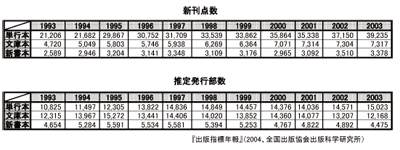
この現象は書店の現場の声とも一致する。新書・文庫の充実した品揃えで知られる八重洲ブックセンターの田中文夫販売部次長兼5階担当フロア長(肩書きは取材時、現宇都宮パセオ店店長)はこう語る。
「『バカの壁』の大ヒットで新書の売上が伸びたとみなさん想像するんですが、総合的にはそれほど変わっていないんですよ。確かに、この7年間ずっと下がってきていた数字の歯止めにはなりましたが、お客さまのキャパシティがある程度決まっていて、その中で動いているだけのような気がします。この先、新書の売上がどんどん伸びていくかといえば、ちょっと疑問ですね」
言い方を変えれば、新書マーケットへの新規参入や新刊点数の増加が新たな客層の拡大につながっていない、ということだろう。
新書の発行元に何を求めるか、との問いに対しては、田中氏はこう答える。
「柳の下にドジョウじゃないですが、養老さんの本が売れたからといって、あちこちで似たような本を出すのはいかがでしょうね。すべての新書が同じ色にならないように、ウチはウチだという個性というか、それぞれの新書が「顔」を持って欲しいと思います」
シリーズとして刊行される新書は、1点ごとの個性の積み上げが全体のイメージを形成していく。行き当たりばったりの粗製濫造はシリーズとしての特色と読者の信頼を失い、やがて淘汰されていくだろう。そうでなくとも市場は飽和しているのだから、淘汰が始まるのは必然である。
そのなかで個性の際立った「顔」を確立し、読者にアピールできるかどうか。そこに乱立する新書シリーズの生き残りがかかっている。
(参考文献)
|