|
仕事熱心な若者が、ある日突然この世を去った。最愛の息子を亡くした母は、なぜ息子は命を落とさなければならなかったのかと問い、裁判をはじめる。互いを思いやる家族の絆は、彼の死によって途切れてしまうのか。
9月1日、東京・品川区のなぎさ会館にて告別式がとりおこなわれることになった。北海道ではなく、東京で別れの場をもうけたことについて、淳子は後にこう振り返る。
「息をひきとった後、会社の先輩だった河村さんが、涙でぐちょぐちょになった顔のまままっ先に駆けつけてくれたんです」
現在はリクルート社を退職し、ジャーナリストとして活躍している河村清明だが、当時、偉(いさむ)とは同じ北大を卒業したこともあり、仕事だけでなく個人的にも親しくつきあっていた。
「偉に寄せてくれる暖かい気持ちが伝わってきて、偉が過ごした東京での4年半で、別れを言いたい人がいることに気づいたの。そして、誰にも一言も言えずに逝った偉も、みなさんに別れを言いたいだろう、と。それで、東京でお別れの会を開くことにしたんです」
告別式は無宗教で、僧侶なし。弔辞の他は焼香と献花だけと決めた。
「あの子は自分のお葬式のあり方について何もいわなかったけれど、私と物事に対する感覚が似ているので、おそらく無宗教を望むだろうと思ったから」
午前10時、告別式が始まった。参列者は会葬者名簿に記された人数だけで350人を超えた。淳子は、偉の妹のまどかと並んで祭壇横の椅子に腰かけた。時折、ハンカチで目もとを押さえるまどかの隣で、淳子は取り乱すこともなく、背筋をしゃんと伸ばし、一点を見つめるかのように佇んでいた。
淳子はその時の心境をこう語る。
「あの時、頭の中はたぶん真っ白だったと思うの。哀しいとか、つらいとかといった感情は置きさり、ともかくこれを乗り切って、偉を早く旭川に連れて帰りたいということしかなかった。『これは偉のお葬式じゃない、偉によく似た人のお葬式だ』と思いこませていたのかもしれない。夫がいれば、泣き崩れることができたかもしれないのだけれど・・・。私がしっかりしなくてどうする、泣くわけにはいかないと自分に言い聞かせていたんだと思う」
淳子は偉が中学1年生のときに夫と離婚している。それからは、自らの生計で偉とまどかを育ててきた。偉の父親は札幌に住んでいるが、病気のためにドクターストップがかかり、告別式のために上京することを断念せざるを得なかった。
「みんな、お前が好きだった」
司会者の合図で全員が起立し、黙祷をささげる。偉の生い立ちや、くも膜下出血で倒れてから亡くなるまでの様子が簡単に紹介された後、関係者から弔辞が捧げられた。
初めに、偉の上司だった「週刊B-ing」編集長(当時)の田中和彦が弔辞を述べた。
「石井へ
石井が突然この世を去ってしまった。
僕はいまだにこのことが実感できないよ。
入社式のスピーチで一躍全社にその顔と名前を知らしめた石井。
先輩の河村には極端に弱く、後輩のMには極端に強かった石井。
でも、どんな形にせよ結局は誰にでも実は愛情深く接していた石井。
企画会議で論議が白熱すると必ず声を裏返して、頭から湯気を立てていた石井。
そして何故かしらその出張先が競馬場のある新潟や京都だった石井。
誰が何と言おうと絶対にカラオケのマイクを握らなかった石井。
生まれて初めての海外がベトナムへの取材だった石井。
そしてそのベトナムで警察に押収されたカメラを『プリーズ、カメラ。プリーズ、カメラ』の単語だけで取りかえした石井。
(中略)
独特の笑い声をフロアじゅうに響かせていた石井。
仕事では遅刻しないのに、レクリエーションだと必ず遅刻して人を待たせた石井。
ゴールデンウイーク、夏休み、年末年始、必ず北海道に帰省していた石井。
『旭川はちょっと寄るだけです』と言いながら実はものすごく家族思いだった石井。
仕事よりも、音楽や映画やスポーツや競馬や読んだ本で僕らを楽しませてくれた石井。
そんな石井をみんな好きだった。
一人の人間として愛していた。
(中略)
倒れる2日前に宮本輝の『胸の香り』の話をしたよね。月曜日に貸そうと思ってたのを今日持ってきたから、ゆっくり読んで今度感想を聞かせてくれよ。
石井、さようなら。
やすらかにお眠りください」
続いて、河村が祭壇の前に進んだ。河村はこみあげてくる嗚咽をこらえ、弔辞を読み上げた。
「石井。
今からオレが何を言うか、ニヤニヤして待っているやろ。このオッサン、変なこと言うんちがうかて、ちょっと心配してるやろ。
そやけど、今日のオレは少し変や。お前の、あの甲高い、でも優しく響く笑い声が聞こえへんようになって、涙が止まらん。何や、目と鼻の真ん中に、カラシでも塗られたみたいや。
同じ大学出て、同じ会社選んだからいうわけでもないやろうけど、よう一緒に遊んだなぁ。お前とのおもろい話なら、屋台に並べて叩き売りするくらいあるで。そやけど、今となってはどれもまぶしすぎて選びようがないから、お前が知らん話をするわ。
金曜日に府中競馬場で夏祭りがあって、いつもの連中と行ってきた。お前とも何回、何十回って待ち合わせた、トキノミノルの銅像の前に集合してな。
いつも貧乏くさい酒ばかり飲んでいるのに、みんなで酒とつまみを持ち寄ったら、えらい豪勢な宴会になったで。花火が上がるのを待つ間、誰が言い出したんか、夕闇にまぎれて芝コースにしのびこんだった。長い直線の真ん中に立って、人のいるスタンドを見るのは不思議な気分やったぞ。
ほんで、これがお前へのおみやげや。競馬場のゴール坂のまん前の芝生やで。いつも一杯寄付してるから、ちょっとくらいかめへんやろて、ごっそり取ってきたった。オレらが応援した馬の汗と、勝った馬の喜びと、負けた馬のいななきがしみこんだ芝生や。これ、お前にやるからな。
花火見ながら、落ち着かん心の中をのぞいて、いろいろ考えてみた。
今回のこと、哀しい言うたらあかんような気がするねん。あと50年もたったら、ここにおるほとんど全員がお前と同じ側におるんやから。それはほんのちょっとした差やろ。いたずらに哀しがっても仕方ないもんなあ。
でも、寂しいぞ。お前の姿が見えんことが、痛いくらい淋しいぞ。過去の、そしてこれからの、いろんなことを、お前と分けあうことができへんのがほんまに淋しいぞ。みんなお前のことが好きやった。お前とは、飽きるくらい一緒におりたかった。
石井、ちょっとだけ待っとれ。
お前のおらん淋しさを味わいつくして、またおもろい話作って、お前に逢いにいくから。
しばらくの別れの言葉は、お前もオレも好きな小説の中の、短いセリフを借りてきた。
石井。
またな」
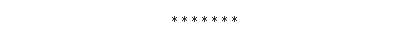
淳子は切なかった。紋切り型の弔辞ではない、熱い語り口調が胸にこたえた。
弔辞と弔電、焼香と献花が終わると、白いカーネーションが棺の中に捧げられた。そして、淳子はあいさつに立った。深々とおじぎをした淳子は、凛と張りつめた表情に、穏やかな口調で切り出した。
「本日は息子のために、わざわざお越しいただき、ありがとうございます。29年という長いとはいえない人生でしたが、心優しく暖かい方たちに囲まれて、充実した密度の濃い日々を送らせていただいたことを、この1週間、いろいろな形で教えていただきました。ただ、母親としましては、あの子がまだしたいこと、思い描いていたこと、やり残したことがたくさんあったような気がします。替わってやれないこの身のつらさが胸に響きます。
アクが強く、我の強い子を、よくここまでみなさまの中で生活させていだたいたと思います。心からお礼を申し上げます。あるいは不愉快な思いをおかけしたこともあるかと存じます。私に免じてどうぞお許しください。一言のあいさつも申し上げないで逝きましたが、息子はお礼を申し上げたかったと思います。ほんとうに、ほんとうに、ありがとうございました」
最後まで気丈な母の姿は、参列者の涙を誘った。
それから数時間後、偉の遺体は火葬され、昇天した。淳子は小さな箱に納まった息子の遺骨を胸に抱きしめた。
帰郷
9月5日、淳子は遺骨を抱いて、まどかとともに秋風が吹き始めた旭川に帰った。自宅に着くとすぐに、テーブルと3段ボックスをリビングに運んで白い布をかけ、急ごしらえで祭壇をこしらえ、遺影と遺骨をおいた。その途端、腰が抜けた。身体が動かない。まさに、腰が抜けた状態だった。
「あまりにつらいことがあると、しばらくの間は防御本能が働き、現実を受け入れられないものなのね。でも、自分の家に帰ったとたん、緊張の糸がぷっつりと切れた。心がほどけきって、ひたすら涙が出るの。何をしても、すべてのことが偉につながり、ぽろぽろと涙が止まらなくて・・・」
偉が使っていた北側の部屋、偉がつけた玄関の壁の傷跡、窓から見える函館本線、目の前を流れる忠別川・・・。ありとあらゆるものが偉に結びついた。涙を流しながら、
「偉、おまえ、どこにいるの?」
となんども問いかけた。
ある時、
「雲の中にいる」
と幻聴が聞こえた。偉が雲の中から飛び出して、帰ってくると信じた。だから、夜になってもカーテンを閉められない。リビングのカーテンを夜も開けっぱなして、偉を待った。
眠れない夜が続いた。うとうとしたと思うと目が覚める。その繰り返し。一番、つらいのは朝だった。目が覚めると、偉の死が夢ではなく現実なのだと思い知らされる。
「あの子に親として十二分なことを何もしてやれなかった」と後悔し、「私はもう十分、人生を生き切った。それなのに、なんで私が生き残って、無限の可能性をもっていたあの子が死ななくてはならないのか。私みたいなものが生き残ってもしょうがないのに」
と自らを責めた。
夕方、空が暮れなじんでくると薄暮の空に向かってベランダから一歩、踏み出したくなる衝動にかられた。「あの雲に吸い込まれたら、偉に会える」と。そして、思った。
〈私はもう一生、笑うことはないだろう。化粧もしないだろう。本を読むことも、テレビも見ることも、映画を見ることもないだろう。私は死んだのだ、偉の死とともに〉
自分の存在感がしだいに消えていく気がした。
どん底から「生」の世界へ
一方、まどかはすっかり別人のように変わってしまった母のことが心配で、夫の元に帰れないままでいた。東京にいた10日間で淳子の体重は5kg以上も落ちた。旭川に帰ってからも、ろくに食事もとろうとしないので、日に日に痩せこけていく。
〈このままでは身体を壊してしまう。もしかすると、自殺するかもしれない〉
と不安で仕方なかった。
3ヵ月前、まどかが結婚する時に偉が「オレは東京にいて母さんに何もしてやれない。おまえが母さんの味方になって、しっかり守ってやれな」と言った言葉が重みを増して迫る。あの時は「また、兄貴風吹かせて」と思ったが、まさか、こういう形で現実のものとなるとは誰が予想しただろう。
まどかは小さかった頃を振り返った。年子で生まれ、1歳しか違わないのに、兄はしっかりもので、何ごとにも秀で、自分はかなわないと感じてきた。
「母と兄は性格が似ているだけでなく、愛読書や映画の趣味も一致していて、いつも共通の話題で盛り上がっていたんです。そんなふたりに私はついていけないものを感じていました。だから、兄を失った母の悲しみの深さは想像を絶するものがありました。生きることに罪悪感をもっていました。そんな母を目のあたりにして、私が替わりになればよかったと思い続けていました」
偉の死から1ヵ月ほどたったある日のことだ。淳子はいつものように偉の写真の前にぼんやりと座りこんでいた。ふっと、斜め後ろからまどかがつぶやいた。
(私がお兄ちゃんの替わりに死ねばよかったのに〉
淳子ははっとして我に帰った。振り返ると、そこには自分と同じように悲しみ傷ついている娘が立っていた。
〈この子をこれ以上、傷つけてはいけない。私にとっては偉もまどかもかけがいのない存在、ふたりとも同じ重さで大切な子どもたち。それなのにお兄ちゃんの方が大事だなんて、そんな風に思わせちゃいけない。私は自分の心の傷や悲しみに埋没していた。まどかが別の形でこんなにも傷ついていたことすら気づいてやれなかった。私は生きていかなくちゃいけない〉
自分を必要としている人間がいる。そのことが絶望のどん底で死を見つめていた淳子を「生」の世界に引き戻した。
(敬称略、つづく)
|