|
冷戦が終わり、諍いも隔たりもない世界が広がる。そんな風に考えたのもつかの間、人々は以前よりも内向きに、自らの殻、国家や民族に閉じこもり始めた。これは一時的な反動なのだろうか。それとも、こうした息苦しさはこれからも続くのか。人々が国家や民族、人種という鎧を剥ぎ取り、自分自身になれる時代はやってくるのか。ジャーナリスト藤原章生氏が、世界各地の現場から、さまざまな人間との出会い、対話を通して考察する。
 |
| ゲレロ州アカプルコ近郊で |
「あーはっはー」という、心底おかしいという笑い声が聞こえてきた。まるで、以前おもちゃ屋でよく目にした笑い袋のような、けたたましい笑いだ。メキシコ湾の安いモーテルの砂浜。目の前には緑の海が広がる。朝から誰もいなかった浜に、地元のメキシコ人が昼食にやってきたのだ。読書に没頭していたため、彼らに気づかなかったが、笑い声で目を覚まされた。
それにしても、あの笑い。知人にメキシコの写真を見せたときのことを思い出した。写真の中で、メキシコの中年男はあごがはずれるほど口を縦に大きく開き爆笑している。メキシコ家庭でのパーティーの一こまだ。知人はいくつもある中で特にその写真に注目した。
「日本人はこういう笑い方はしないね。やっぱり文化が違うんだろうね」
笑い袋が面白いのと同時に少し気味悪いのは、あの笑い方にあまり馴染んでいないせいだろう。寄席や会社員が集まる飲み屋で耳にする笑いはもう少し短い。ドッと爆笑するがすぐに静まり、続けざまにまたドッと笑う。大波小波の振幅が激しく、谷の部分、つまり笑いの中にきちっと短い静寂が折り込まれている。
ところがメキシコ人の笑いはもっと連続的だ。高波が落ちないまま延々と押し寄せるように、あっはっはー、はーと、放っておいたらいつまでも止まない。わざと笑っているのでは、と疑いたくなるほど妙に長い。10年前、世話になったメキシコ家庭では、そこのセニョーラ、アンヘリータを前に私が冗談や下品なスペイン語を口真似するたびに、「アキオ・パパー」と私の名を甲高い声で叫び、「あーはっはー」を4回ほど繰り返し、涙を流さんばかりだった。
 |
| メキシコ市レフォルマ通りで |
自分も中学生、いや20代のころまでは大声を出して笑うこともあったが、最近は腹がよじれるほどのことがない。脳の中から笑いを呼び覚ます子供らしさが消えたのでは、と思ったりもする。そうなら、メキシコ人には子供らしさが大人になってもしっかり残っているのかもしれない。
普段は近所でアイロンかけをして暮らす子沢山のアンヘリータは、生活苦から苦虫を噛み潰した顔をよくしていたが、笑える機会とあればとことんといった心意気があった。つまり、日々笑いを求めているのだ。悪意であれ善意であれ、とにかく笑いたい。そしていざ笑える話や出来事に直面すると、「この機会逃すものか」と出来るだけ引き伸ばす。無意識にそんな気構えがあるから、笑いが尾を引くのではないだろうか。
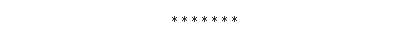
そんなことを考え、隣に陣取る人々に耳を傾けると、当初の爆笑は収まり、笑いは小波になっている。子供を浜で遊ばせる間に酒盛りをしようという3組ほどの中年カップルである。身だしなみから暮らしぶりは中の上といったところだ。
本を読むふりをして彼らに注意を傾けると、ときどき「チーノ」や「チニート」と東洋人の総称を口にしている。彼らは私とその連れのことを話題にしているようだ。ここで、もうけ物なのは、私たちがスペイン語を話さないという先入観が彼らにあることだ。ペルー辺りはそうでもないが、中国系の少ない地では、「チーノはまともにスペイン語を話せない」という思い込みがある。しかも、こちらが当初、本から目を離さず何の反応も示さなかったため、そう確信したようだ。それをいいことに彼らは手近にいる我々を歓談の種にしている。
異文化を知るのにインタビューや座談はあまり有効とは言えない。人は取り繕うし、少しでも善人ぶりたい虚栄がある。身構えれば、「庶民の本音」は顔を出さない。だが、日ごろ無造作に耳に飛び込んでくるおしゃべりは時に格好の材料となる。
「でも、あれ、本当のチーノじゃないんじゃない。グリンゴ(米国人)かもよ。ハポネス(日本人)かコレアーノ(韓国人)かも」「だけどチーノの親戚だろう」「そりゃそうだ。うちの子もチーノだからね」と、ここでまた爆笑。メキシコでは髪の毛の縮れた人や切れ長の目の人をこう愛称で呼ぶことが多く、「うちのチーノ」はそれを指す。それにしてもこんな話で大笑いできるその心が羨ましい。
「お、チニータ(東洋系の女)が来た。見ろ、結構、きれいじゃないか」「肌、白いなあ」と男2人が言うと、だみ声の女性が「フェア(醜い)!」と大声を上げ、「むきになるなよ」と男が返し、また小爆笑。
「だけどよ、アジア系の女は・・」とリーダー格の男が何やら性的な薀蓄を講釈し、今度はひそひそと下卑た笑いを続ける。
こうした機会は滅多にあるものではない。自分ひとりで問題を立て、それをあれこれ考え解いていく良いきっかけとなる。
 |
| メキシコ市の中心街で |
チーノを笑う彼らの心理とは、どういうものなのか。こうした異民族に対する個人個人の意識、一見「差別」とも思えるような感覚は、上段から論理で解いていくよりも、身近な経験と、自分自身の洞察を照らし合わせ、各論を積み上げていく方が、答を得やすい。私は以前、南アフリカに暮らしていたとき、そんな考えに至った。はたから見ると、黒人と白人が単に背を向けたまま対立している社会だが、その中にいる人々の多様性、混血性、そしてそれぞれの意識は網の目のように複雑に絡み、一つ一つを精密機器の配線コードをたぐるように解いていかなければならなかったからだ。
他者を差別する感覚は恐怖と少し似ている。それは個人の頭の中で作られ、目の前の現実や理屈とは直接関わりなく、いくらでも膨らみ、萎む。その日の天候にも左右される位だ。そして、ほんの些細な被害経験や幼児的な想像力が、論理で積み上げた平等、平和といった理想を容易に打ち砕いてしまう。
初めて留守番を任された幼児がその想像力から自宅を幽霊屋敷と思い込んでしまうように、他者を見る個人の差別感覚も、それぞれの想像の産物という面が強い。
彼らの会話を自分に立ち返って考えてみると、体験の貧困さからか合点のいかない部分も多い。日本に暮らし、ある温泉に行ったら隣に見慣れない外国人がいたとしよう。それがどんな国の人であれ、笑いの対象にするという感覚は自分にはないような気がする、と一瞬思う。でも、どうだろうか。私は今から30年ほど前、「インド人もびっくり」といった表現を何の気なしに使っていた気がする。自分にとって初めての海外、インドの経験を「芝生で寝ていたらいきなり按摩屋が来て、肩もみ始めてさあ、1ドラ、1ドラってうるさくってよお」などと友人に誇張も交えて語り、お笑いの種にしていたことがある。
トルコ風呂という言葉が公然と使われていたころのトルコ人に対するジョークなども結構あったのではないだろうか。それに日本には、黒人を性的に活力のある存在とみなし、ラテン人は常に明るく祭りのことしか考えていないといった思い込みがいまだにあるのではないか。それに私の親たち、大正や昭和の初めに生まれた世代が幼いころ、中国人や朝鮮人の話す日本語を口真似して笑うのは、日常の出来事であったようだ。そう考えれば、メキシコの庶民の幾らかが、チーノを見るとついプッと笑ってしまう感覚もある種普遍的なものかも知れない。
 |
| メキシコ州の遺跡テオティワカンで |
ただ、そこにはもう一つ別の要素が絡んでいる。それはインディオ、つまり、少なくとも1万年以上前からこの大陸に暮らす、アジアからベーリング海峡、または太平洋の島々を渡ってきたと言われる先住民族の存在だ。共同通信社の『世界年鑑2004』によると、メキシコには25%のインディオと60%のインディオとスペイン系白人の混血がいる。つまり、85%はインディオの血を引いていることになる。
私が10年前に暮らしたメキシコ西部の都市ではスペイン系の顔つきをした混血が目立ったが、今暮らしている首都メキシコ市は私に言わせれば「インディオの地」である。特に低所得者層の多い地下鉄に乗ると、一見暗そうな人々の骨格はアメリカ・インディアンを思わせ、歴史が少し違う方向に動いていれば、北米を含むアメリカ大陸すべての地下鉄でこうした元祖アメリカ人が黙々と体を揺らしている、とそんなことを考えたりもする。
インディオ、そしてその混血という題材はメキシコ人論の第一人者である哲学者、サムエル・ラモスや詩人、オクタビオ・パスが説くように、メキシコ人の本性を探るのに避けて通ることはできない。ラモスはメキシコ人の性格をインディオの出自と絡め、この国に入り込んできたスペイン人、フランス人、米国人を前にした「劣等感」をキーワードに解いている。パスも名著『孤独の迷宮』の中で「イーホ・デ・チンガーダ(犯された母=インディオ=の子)」というメキシコ人がよく使う侮蔑語などを題材に、混血のメキシコ人は、踏みにじられ、そして自ら踏みにじってきたインディオの血から決して解放されないと説いている。
「現在のメキシコ人に関する限り、彼らは自分自身であることを望まないか、または、あえてそうなろうとしないかのどちらかである」
つまり、自分はどこから来たのか、自分とは何者なのか、自分を誇れる、自分を支えてくれる最後の拠り所はどこにあるのか、という問いかけ。つまり、民族であれ国籍であれ常にどこかの集団に属し、頼らないと生きていけない弱々しい個人たちがすがりつく基盤が、メキシコではそもそも国ができたころから大きく揺らいでいるという考えだ。メキシコ人によるメキシコ人論が学者やメディアでいまだに盛んな理由もそこにある。
パスはさらにこう論じる。
「メキシコ人は、インディオにもスペイン人にもなりたくない。彼らの子孫であることも望まない。彼らを否定する。そしてメスティソ(混血)としてでなく、人間であるという抽象として活気づくのである。無の子となる。彼は自分自身から始まるのである」
 |
| メキシコ市コヨアカンで |
この論には啓蒙家であるパスの希望が多分に込められている。パスがこれを記してからほぼ半世紀が過ぎた。だが、現実に彼の言う「無の子」、出自や国籍から一切自由な人間がどれほど生まれたろうか。このメキシコに限らず、そんな帰属という感覚から自由でいられる人間が、いまこの地球上にどれだけいるのだろうか。そういう時代は本当にやってくるのか。
「何を偉そうに、あんただってインディオみたいなものじゃないか、インディオ!」「お前さんに言われたくないね。インディア・マリア!!」
隣では相変わらず小さな爆笑が続いている。話題はチーノの女の体からいつの間にか、自分たちの方へ向いたようだ。やはり、ここでも「インディオ」がキーワードだ。ひそかに他者をからかい笑った末、自分たちを省みる。そして最後は溜め息をつく。彼らもメキシコ人である。とどのつまりは結構、内省的で自分の存在にとことん自信を持てない部分を備えている。それをどうにか笑いで吹き飛ばす、というわけでもないだろうが、あの腹がよじれるほどの笑い声、やはり羨ましい。
(敬称略、つづく)
日本語文献
『孤独の迷宮』(オクタビオ・パス著、高山智博、熊谷明子訳、法政大学出版局)
『くもり空』(オクタビオ・パス著、井上義一、飯島みどり訳、現代企画室)
「メキシコにおける人と文化」(『ラテンアメリカ 人と社会』所収、角川雅樹著、新評論)
|