|
彼に向かって、心の底をぶちまけた。君はまさに自信満々の様子だ。そうではないか。しかし、その信念のどれをとっても、女の髪の毛一本の重さにも値しない。君は死人のような生き方をしているから、自分が生きているということにさえ、自信がない。私はといえば、両手はからっぽのようだ。しかし、私は自信を持っている。自分について、すべてについて、君より強く、また、私の人生について、来るべきあの死について。そうだ、私にはこれだけしかない。しかし、少なくとも、この真理が私を捕らえていると同じだけ、私はこの真理をしっかり捕らえている。私はかつて正しかったし、今もなお正しい。いつも、私は正しいのだ。私はこのように生きたが、また別な風にも生きられるだろう。私はこれをして、あれをしなかった。こんなことはしなかったが、別のことはした。
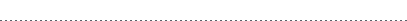
『異邦人』は1940年(発表したのは1942年)、当時、フランスの植民地だった北アフリカのアルジェリアで生まれ育ったフランス人ノーベル賞作家、アルベール・カミュが書いた小説である。
主人公のムルソーは海運会社で事務員をしている平凡な独身男性だが、養老院で暮らしていた母の葬儀で涙を見せずに居眠りをし、葬儀の後、海水浴に行ってナンパした女マリイと映画を見てセックスをすることに、何の後ろめたさも感じない男だ。そのムルソーは、友人に誘われて出かけた海岸で、アルジェリア人との諍いに巻き込まれ、アルジェリア人を殺してしまう。
事件自体は、フランス人が植民地のアラブ人を、諍いが原因で殺した平凡な出来事であり、普通なら加害者のムルソーが死刑になるような事件ではない。しかし、法廷で殺害の動機を問われたムルソーが「太陽のせいだ」と答え、葬儀で涙を見せなかったことや、葬儀の日の夜に、その日海で知り合った女と関係を持ったことが明らかになるに従い、事態は深刻な様相を呈していく。ムルソーのような人物は、社会がその生存を容認することが出来ない存在であることが示唆される。ついには、ムルソーは断頭台に送られることになるのだが、ムルソーは、アラブ人殺害の廉で処刑されるのではなく、母の葬儀で涙を見せなかったことで、社会から抹殺されることになるのである。
初めて『異邦人』を読んだのは、高校2年生の時だった。私は、日本の社会で生きていかなければならない子供に、「ノア」と名づけるようなキリスト教の伝道師の家庭に生まれ育ち、月刊プレイボーイのピンナップを見てマスターベーションをしたり、女の子とセックスしたいと思ったりしただけで、死ななきゃならないと思うほど罪の意識を感じ、一日に何度も死ななきゃならないと思わなければならないような、痛々しくも気の毒な青春を送っていたので、ムルソーとの出会いは、衝撃だった。
カミュにノーベル賞作家の栄誉をもたらした『異邦人』は、不条理を極限まで追求した作品だと理解されている。が、高校時代の私は、違う読み方をしていた。キリスト教の倫理観に雁字搦めになっていた私にとって、ムルソーは不条理を生きている人ではなく、キリスト教社会と闘う憧れのスーパースターだった。
ムルソーとは例えば、このような人である。
マリイと一緒に過ごした翌朝、マリイが「あなたは私を愛しているか」と尋ねる。ムルソーは答える。「それは何の意味もないことだが、恐らく愛していないと思われる」と。しかし、ムルソーはマリイの笑顔をみると欲望を感じ、彼女にそばにいて欲しくてレストランに誘ったりするのである。
裁判では、弁護士が葬儀の日に泣かなかったのは感情を押し殺していたと証言するように勧める。が、ムルソーは「言えない。それはうそだ」と断る。
高校時代の私は、ムルソーは不条理の人というよりは、自己をありのまま肯定し、社会が押し付けてくる価値観と闘う人なのだと理解した。だから、キリスト教倫理観の中で、自己否定を苦しんできた私には、ムルソーはスターだったのであり、私は、ムルソーのようになりたい、と強く思った。そして、ムルソーとの出会いにより、私は自己否定の地獄から徐々に開放され、キリスト教的世界と決別し、新たに生まれ変わることが出来たのだと思う。
そういう訳なので、あなたの人生にとって、一番重要な意味を持った本を一冊上げよ、と問われたら、私は躊躇なく、カミュの『異邦人』と答える。また、この作品は、私が折に触れ、何度も読み返してきた作品でもある。
何度読み返しても、私の思いはそう変わらない。むしろ、ムルソーは、「異邦人」を容認しようとしない社会の気味の悪さや恐ろしさと果敢に闘った、一風変わった男なのである、という見方が、読み返す度に強くなっていく。
母の死や、恋人への愛、そうしたものに格別の意味を見つけることはできない。それは、暑いとか、太陽が眩しいとか、首が痛い、といった生理的なことと、同じような意味しか持たない、とムルソーは言う。しかし、ムルソーは、誰かが母の死を悼む気持ちや恋人を愛する気持ちに意味がないと言っているのではない。人間ならばそのような気持ちを持つべきであると、社会が人の生のあり方を一方的に強制することに対して、ムルソーは「ノン」(否)と、叫んでいるのだ。
そのように読めば、『異邦人』は今なお、私たち現代人にとって重要な意味を持つ作品である。なぜなら、そのような社会の個人に対する、ある種の価値観の押し付けや強制は、ここ10数年の間、日本社会でその傾向が顕著となってきているからである。
|
 |
 |
岩本 宣明
1961年生まれ。毎日新聞社会部記者などを経て93年文筆家として独立。同年、現代劇戯曲『新聞記者』で菊池寛ドラマ賞受賞。
主な著作:


『異邦人』
カミュ/窪田啓作訳
新潮文庫
|
|