|
2006年にワールドカップが開かれるドイツ。過去に3回の優勝を誇るドイツサッカーの本質とは何か。ドイツに詳しい、自他共に“サッカーマニア”と認める明石真和氏が現地での体験をまじえ、ドイツとドイツサッカーについて連載する。
 |
| ベルリン・オリンピックスタジアム |
私がサッカー・ドイツ代表に興味をもった直接のきっかけは、1970年の第9回ワールドカップ(W杯)メキシコ大会であった。サッカーそのものを知ったのは、もう少し前のことで、1964年東京と1968年メキシコの両オリンピックにはさまれた時期である。
東京オリンピックでベスト8に進出した日本代表チームが、次のメキシコオリンピックでの活躍を期待され、子供向けの雑誌にも「サッカー紹介」記事や、サッカーを題材としたマンガが掲載されるようになっていた。
ふだん自由に使っている「手」があるのに、なんでわざわざ「足」を使うのだろう・・・。「ヘディング」って本当に頭でボールを扱うのだろうか・・・。そんな素朴で単純な疑問が、最初に興味を持ったきっかけだったように思う。とはいえ、実際には、たまに小学校の校庭でボール蹴り遊びをするぐらいで、ことさらこのスポーツにのめりこんでいったわけではなかった。
ましてや、日本にまだサッカーのプロ組織がなく、オリンピックこそが一番の目標とされていた頃の話である。W杯も、「アマチュアだけのオリンピックより、さらにレベルの高い大会」という噂をおぼろげに聞いていた程度で、具体的なイメージなど何ももっていなかった。現在のように大々的なテレビ中継もないあの当時、サッカー関係者やよほどのファンでもないかぎり、W杯の存在すら知らない人がほとんどであったろう。
その頃、1960年代は、メジャースポーツといえば、野球がすべてといってもよい時代である。故郷の千葉県銚子市が殊に野球の盛んな地域だったこともあって、私が小学校3、4年の頃には、放課後や日曜日にちょくちょく仲間たちと草野球をしていた。ユニフォームなど贅沢品であり、みんな普段着のまま公園や空き地に集まって、三角ベースの野球をやった。
そうやって毎日のようにいろいろな仲間と遊んでいると、自然に上手下手が分かってくる。上手な子は、とにかく足も速くパワーもあって、私などは、どうしてもかなわない。小学校高学年になると、これらの運動神経のよい少年たちはみんな野球部に入部していった。将来は有名な県立銚子商業高校に入って甲子園をめざし、できればプロに・・・というのが、彼らの夢であった。我が故郷にかぎらず、日本全国、どこへ行っても似たような状況であったと思う。
野球の上手な子供たちは、陸上、水泳、ドッジボール、相撲・・・と、なんでも得意な万能選手であった。市の小学生大会ともなれば、どのスポーツでもいつも同じ顔ぶれがそれぞれの学校の代表に選ばれ活躍していた。実際、彼らの多くが銚子商業高校野球部に進み、高校3年生になった1974年、夏の甲子園大会で全国制覇を果たすのである。ただ、そんな土壌をもつスポーツの盛んな町であるにもかかわらず、市内のどこの小・中学校にもサッカー部だけはなかった。
中学になると、クラブ活動はますます盛んになり、同級生の多くが運動部に入部していった。バスケット、バレー、陸上、テニス、体操・・・。活動時間になると、それぞれのクラブの選手が、あちこちで喚声をあげて走り回り、花形クラブの野球部などは、グラウンド全面を使って練習を始める。
メキシコW杯、西ドイツ監督はヘルムート・シェーン
既に前年の秋、日本代表チームはメキシコオリンピックで銅メダルを獲得しており、全国的にサッカー人気が高まりを見せていたはずなのだが、私の田舎ではサッカー独特の「白黒亀の甲ボール」すら、まだ珍しかった。それでも小学校時代との違いは、校庭に体育授業用のサッカーゴールが据えられていたことである。放課後になると、いつしか自然発生的に、何名かの生徒がこのサッカーゴール周辺に三々五々集まり、職員室から借りてきたボールを蹴り合うようになっていた。私を含め、みな既存の運動部には所属していないものの、サッカーには興味をもっている連中であった。飛び交う野球のボールに注意を払いながら、校庭の片隅で「シュートごっこ」をする日がつづいた。
 |
「サッカーの名場面集100」に掲載されたシェーン
100 Hightlights Fussball
Weltmeisterschaften 1930-1998
©1998 by SVB Sportverlag Berlin Gmbh |
そんな中学時代の冬休みのことである。私は、ある日ふと思いたち、家の庭でひとり密かにボールリフティングの練習を始めた。「いつも一緒にボールを蹴っている仲間より、少しでも上手くなってやろう」今ふりかえれば、きっとそんなことを考えていたのであろう。
最初のうちは1、2回蹴るだけでボールが地面に落ちてしまう。根気よく、毎日練習した。「今日は5回できたぞ」・・・「次の目標は20回だ」・・・こう自分に言い聞かせながら、ボールを落とさずに何10回か連続して操れるようになってくると、それだけでうれしかった。
この「秘密練習」の成果はすぐ現れた。3学期の体育のサッカーの授業では、周囲の友人たちや運動部所属の同級生よりボールコントロールがうまくなっている自分に気づいた。習志野市や船橋市といったサッカーの盛んな町のある千葉県西部地区と違い、銚子市を含む東部では、足でボールを扱うこのスポーツはまだまだなじみが薄く、運動能力の高い者でも、ことサッカーに限っては勝手が違っていたのである。私がスポーツ万能の同級生たちに伍して、あるいはそれ以上にやっていけるという自信を得た、ただひとつの球技がサッカーなのであった。
サッカーに興味をもつと、当然のように視野が世界に及んでいくようになった。ヨーロッパや南米では、どんなふうにサッカーが行われているのだろう。どんな選手がいるのだろう。あれやこれや思いめぐらすのだが、本場の情報はなかなか入ってこなかった。
そんな中、唯一、外国サッカーの香りを伝えてくれたのが、東京12チャンネル(現テレビ東京)で放映されていた「ダイヤモンドサッカー」だった。アナウンサー金子勝彦、解説岡野俊一郎の名コンビで、サッカーファンの間では、今も語り草となっている伝説の番組である。開始当初は、主としてイングランド・リーグが紹介されていた。異国のサッカー場。グラウンドのすぐそばまで張り出している観客席。スタンド全体が揺れるような応援風景。きれいに刈りそろえられた芝生。その上を行き来する白いボール。すべてが新鮮だった。
そのダイヤモンドサッカーが、1970年から71年にかけて、1970メキシコW杯全32試合のほとんどを放映してくれた。日本で定期的にW杯の映像が紹介されたのは、この時が初めてではないだろうか。週に一回、たった45分の番組であり、今週が前半で来週が後半という今から考えると非常にのんびりした録画放送であったが、毎回食い入るように画面をみつめていた。
優勝したブラジルの王様ペレ。ボビー・チャールトン、ボビー・ムーア、ゴードン・バンクス、マーチン・ピータースといったイングランドの名選手達。それにもまして私の心をうったのが、3位になった西ドイツの戦いぶりであった。闘将ウーヴェ・ゼーラー、優雅なフランツ・ベッケンバウアー、悲愴感漂うベルチ・フォクツ、得点王ゲルト・ミュラー、ドリブルの天才ラインハルト・リブダ・・・。ひとりひとりが個性的な選手達。そして、どんなに劣勢になっても、最後まで決してあきらめないドイツの魂。もともとドイツという国に興味をもっていた私は、これをきっかけとして一気にドイツ・サッカーに夢中になっていった。なかでも特に心惹かれたのが、強烈で多彩な個性の選手達を指揮するヘルムート・シェーンという監督の存在であった。
この頃から、ようやく日本でもW杯という言葉が人々の口の端にのぼるようになり、少しずつではあるが海外のサッカー情報がはいってくるようになる。そんな当時を知るファンの中には、1970年代のドイツ・サッカーの素晴らしさを記憶に留めておられる方も大勢いらっしゃるだろう。1970年メキシコW杯での3位に続き、1972年ヨーロッパ選手権では、美しく流れるような華麗なサッカーで圧勝。余勢をかって、1974年自国開催のW杯でも優勝した。そんな常勝ドイツ代表を率いたのが、ヘルムート・シェーンなのであった。
ドイツ・サッカー黄金時代は、ちょうど私の中学・高校時代に当たっていた。入学した高校には、同好会から昇格したばかりとはいえ、本式の「サッカー部」が存在しており、私はすぐに飛び込んだ。こうして、「いつかドイツへ行きたい」と願いながら、毎日グラウンドでボールを蹴る日が続いた。その一方で情報収集も怠りなく、当時まだ月刊だったサッカー雑誌2種を毎月こころまちにしては、ドイツ代表や選手達の記事を読みあさった。ただ、試合の結果やそのコメント程度のものが大多数で、シェーン監督の経歴や人柄に直接ふれるものがほとんどなく、歯痒い思いは消えなかった。
アルゼンチンでの敗退、黄金時代の終焉
 |
シェーンの自伝
Fußball 表紙
©1978 by Verlag Ullstein GmbH. |
その後、長年の夢がかなって、大学時代の1978年、西ドイツに留学できた時、既にドイツ・サッカーは端境期に入っていた。ゲルト・ミュラーやベルチ・フォクツといった黄金時代の憧れの選手達は既に引退が近く、ベッケンバウアーはその活動場所をサッカーの新天地アメリカに求めて海を渡ってしまっていた。その一方で、カール・ハインツ・ルムメニゲに代表される若手達が、栄光を1980年代に引き継ぐべく台頭してきていた。かつての黄金時代の終焉、そして新しい時代への期待をこの身に感じて暮らした一年であった。
今ふりかえれば、その象徴ともいえる出来事が、シェーン代表監督の引退であったように思う。1978年6月、西ドイツ代表チームは、2大会連続優勝を目指したアルゼンチンW杯で、アメリカからベッケンバウアーを呼び戻すことができず、チームを固定できないまま戦っていた。それでも1次リーグを突破し、ベスト8に残った2次リーグでは、イタリア、オランダと引き分けた。最後のオーストリアとの一戦は、もうひとつのオランダ対イタリア戦の経過をにらみながらの試合となり、大差をつけて勝てば決勝に、悪くても引き分ければ3位決定戦には進めるという状況であった。ところが、シーソーゲームの末、1931年以来一度も負けていなかった隣国オーストリアに、2:3という47年ぶりの歴史的な敗戦を喫してしまう。その結果、決勝はおろか3位決定戦にも進出できなかった。14年間代表監督をつとめ、4回のW杯にドイツを率いた男、ヘルムート・シェーンのこれが最後の舞台となった。それでも、私にしてみれば、「シェーン監督の時代」にどうにか間に合った・・・というのが実感だった。
1978年秋、後任監督にそれまで助手を務めていたユップ・デアヴァルが就任し、シェーンは引退した。それと期を一にして、彼の自伝 Fußball(「サッカー」、Ullstein社刊)が刊行された。非常におもしろい本であった。憧れたドイツ・サッカー黄金時代のエピソードが満載で、そのうえ戦前・戦中の事情にも言及されていた。少年時代のシェーン監督への「心のかわき」を癒せる心地がした。今、「人生の一冊を」と問われれば、私はためらわずにこの本を挙げる。
「誰よりもうまくなりたい」
 |
| 空襲によって被害を受けたドレスデンの街 |
ヘルムート・シェーンは、1915年9月15日にドイツ中東部ザクセン州の古都ドレスデンに生まれた。ドレスデンは、第2次世界大戦中、連合軍の爆撃によって大きな被害を受けたエルベ河畔の都市で、「ドイツのフィレンツェ」と称えられた美しい町である。
父親のアントン・シェーンは、ドレスデンで美術品の骨董商を営んでおり、ヘルムート少年は、サッカーとは直接何の関係もない家庭環境に育った。母親はすらりとした優しい人だったようで、身長が1m90cmを越すシェーンは、「私の長身は母から受け継いだ」と記している。
路上や原っぱで近所の子供達と草サッカーを繰り返すうち、このスポーツの魅力にとりつかれた彼は、「誰よりもうまくなりたい」と、懸命に技を磨くのであった。こうして年ごとに上達していき、地元のザンクト・ベノ・ギムナジウムを卒業する頃には、名門ドレスデン・スポーツ・クラブ(DSC)でも将来を嘱望される選手に成長していた。
ギムナジウムとは、日本の中学と高校を合わせたような9年制で、本来大学進学を希望する生徒が通う学校である。卒業後、大学での専門教育にスムーズに入っていけるようなカリキュラムが組まれ、第2外国語を初めとする一般教養までカバーしているため、レベルからすれば、現在の日本の高等学校よりも、むしろ戦前の旧制高校に近いかもしれない。その頃のサッカー選手の多くが中卒の時代である。経済的事情により最終的に大学進学を諦めたとはいえ、まだ進学率の低かった戦前のドイツで高等教育を受けていたシェーンは、選手としてはかなりのインテリであったといえよう。
彼の卒業時の成績を日本式の5段階評価に直してみると、英語とフランス語が5、ドイツ語(つまり国語)とラテン語と体操が4、数学と化学が3・・・という具合に、外国語に秀でた生徒であったことが分かる。体操が4というのはちょっと意外な気もするが、たぶんこれはドイツ伝統の器械体操を中心とする科目だったためではないかと想像できる。シェーンにとっては、得意なサッカーとは、また勝手が違っていたのであろう。
16試合で17得点
ギムナジウム在学中から既に、1936年のオリンピックを狙う若手代表候補として、「帝国首都ベルリン」での研修にも呼ばれるようになっていた。このスポーツ研修では、ドイツ全国から、あらゆる競技種目の500人の選手がベルリンに集められ、ふるいにかけられる。ある時など、軍服に身をかためたアドルフ・ヒトラーがこの研修所に姿を現し、34名の若手サッカー代表候補が整列して迎えたという。1933年1月に政権の座についてからまだ2ヵ月が過ぎたばかりのヒトラーは、ベルリンオリンピックを3年後に控えた「国民の期待の星達」を激励に訪れたのであった。シェーンは、ヒトラーを間近で見た「時代の証人」でもあったわけだ。
結局、ベルリンオリンピックは膝の怪我で棒にふったものの、1937年11月の対スウェーデン戦に、22才の若さで代表デビューを果たした。この試合、ドイツは5:0の勝利をおさめ、初陣のシェーンはそのうち2ゴールをあげるという大活躍をして、注目を浴びることになる。
その頃のドイツにはプロリーグがなく、シェーンは故郷ドレスデン近郊にある「マダウス」という製薬会社に外交員として勤務しながら、DSCでのプレーを続けていた。その間もドイツ代表に選ばれ、足かけ5年間で16試合に出場して17得点をあげるほどのスター選手となった。こうして少年時代からの夢がかなって、一流サッカー選手の仲間入りを果たしたのだが、時代は若い彼の運命をもてあそぶかのように戦争に突入してしまう。
サッカーで痛めた左膝に持病をかかえていたシェーンは、徴兵検査で不合格となり、そのまま国内に留まることができた。後に、大戦末期の総力戦の中で歩兵として召集された時にも、「戦争遂行上の重要企業」とみなされていた勤務先の製薬会社が兵役免除に尽力してくれたため、たった3週間でもとの職場に復帰することができた。しかも、薬品をドイツ全土に手配する仕事や、輸送トラックの見張り役などという比較的軽い作業の部署であった。DSCや代表チームの同僚の多くが命懸けの前線に送り出されている時に、直接の戦闘とは無縁の場所に身をおけたのは、大いなる幸運であったといえるだろう。
スパイクを軍靴に、代表候補選手77人中33人が戦死
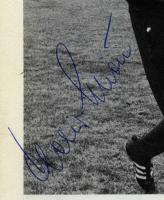 |
| シェーンから筆者への直筆サイン |
ヒトラーは、あまりサッカーが好きではなかったらしい。もともと画家を目指していた彼には、スポーツは興味の対象ではなかったのであろう。スポーツの具体的な目標を単に「兵役のための予備訓練」とみなしていたともいわれる。
ところが、国際的な影響力という点から見れば、サッカーやその国際試合は世界に対して「平和国家ドイツ」をアピールし、各国から信頼を勝ち得る格好の舞台である。そのあたりを宣伝の巧みなナチスが見逃すはずがなく、あの手この手で、政治がスポーツに介入するようになる。
サッカー代表選手は、「ハーケンクロイツの付いた帝国の鷲」をユニフォームの胸に抱き、試合前の国歌吹奏では、戦争映画でおなじみの右手を斜め上に掲げた「ドイツ式(ヒトラー式)敬礼」を強制されるようになった。両国国歌の演奏中、ずっと右手を挙げたままのポーズをとるのである。当時のドイツには正式の国歌である「世界に冠たるドイツ」と並んで「ホルスト・ヴェッセルの歌」という第2国歌まであり、試合前には相手国も含め、つごう3曲分の歌が流れるのだ。この間、直立不動でずっと右手を挙げて立っているのは、肉体的にもかなり大儀であったろう。シェーン自身も「できることなら左手で右手を支えたかった。・・・痙攣して揺れる手が、ちょうどメインスタンドに向かって挨拶しているような格好になった」と記している。笑うに笑えない話だが、その姿を想像するだけで、なんとなく可笑しい。
そんな時代の1934年、イタリアW杯が開かれ、ドイツはオットー・ネルツ監督のもと、3位という立派な成績を残した。ラジオで聞き知った国民は熱狂し、政府首脳部は、あらためてサッカーの影響力を認めることになる。こうして翌1935年には、なんと17もの国際試合が組まれたのである。もっとも当時のことであるから、対戦相手は北欧の国々やオランダ、フランス、ベルギー、イングランドといった周辺諸国に限られていた。代表チームの国際試合の前には、2週間の合宿がセットされていたため、アマチュアだった当時の選手達は、仕事との両立に苦心したようである。
このような、「ありがた迷惑」ともいえる政府のバックアップのもと、1936年のベルリンオリンピックでは、金メダルが大いに期待されていた。ところが、意外にも2回戦でノルウェーに敗れてしまい、サッカーを初めて観戦した総統ヒトラーを失望させ、怒りをかってしまう結果となった。
ネルツには、それでも辞任の意思はなかったが、紆余曲折を経た末、後任としてゼップ・ヘルベルガーが就任する。ヘルベルガーは、長い間ネルツの助手を務めており、ネルツ自身も彼の実力は認めていた。ただ、パワーに頼るネルツと、技術やパスワークに重きをおくヘルベルガーのサッカー観の違いもあり、ベルリンオリンピックでは、ヘルベルガーは蚊帳の外におかれていたのだ。このあたりの後任人事をめぐる「静かな権力闘争」についてはシェーンの本筋からはずれるので、また別の機会に改めて紹介したい。
新しく監督に就任したヘルべルガーのさしあたりの目標は、1938年のフランスW杯と1940年に予定されているヘルシンキオリンピックであった。ところが、W杯を目前にしてナチスは隣国オーストリアを併合してしまった。当時のオーストリアはヨーロッパでも有数のサッカー強国であり、ヘルベルガーは、事実上2つの国の代表選手を融合させるという難題を抱えることとなった。結果として、この融合はうまく機能せず、W杯では早々とスイスに敗れ去った。
また、1940年のオリンピックは、本来東京での開催が決まっていたのだが、戦争のため返上となり、招致を最後まで争ったフィンランドの首都ヘルシンキに変更されるという経緯があった。最終的には、ヨーロッパの雲行きもあやしくなり、ヘルシンキオリンピックもけっきょくは中止になってしまう。
それでも、ドイツの国際試合は、スウェーデンやスイスといった中立国を相手に、まだまだ続けられていた。1941年4月20日、ドイツチームはベルンでスイスと対戦し、0:1で敗れた。この日は、よりによってヒトラーの誕生日であった。ゲームに出場したシェーンは、この敗戦の感想を「これは、国家に対する反逆罪か、不敬罪に等しいかも・・・」と冗談めかして書いている。事実、この試合の後、「今後、少しでも思わしくない結果になりそうな時は、スポーツ交流をしないように」という、宣伝大臣ゲッベルスからのお達しがあったという。
戦争が激しくなるにつれ、1942年11月22日の対スロヴァキア戦をもって、ドイツ代表の試合も中断を余儀なくされた。選手の多くはスパイクを軍靴に履き替え、前線に赴くのであった。当時の代表選手は「総統ヒトラーの政治的兵隊」とみなされており、「サッカー代表選手は、兵隊としても模範兵でなくてはならない」とされる、そんな風潮であった。その頃の代表選手候補77人のうち、33人が戦死したという記録が残っている。生き残ったものの片腕を失い、それでもサッカーを続けた選手や、試合日に野戦病院から駆けつける選手もいたという。シェーンは、そんな時代に現役生活を送っていたのである。
戦火のもとでの選手権、シャルケ04 vs.DSC
 |
| 筆者のシャルケ04会員証 |
ヒトラー政権下でのドイツ国内のサッカーは、全土がガウ(Gau)と呼ばれる16地域に区分され、各地域でそれぞれ10のトップチームがリーグを形成していた。この各地域のチャンピオンが、さらに全ドイツ選手権を争う仕組みになっていた。
ガウとは、もともと「川沿いの沃野」といった意味合いだが、古代ゲルマン時代の行政区画であったようだ。それをナチスの時代に大管区の名称としたのである。このガウは、ナチス・ドイツが周辺の国や地域を併合するごとに変わっていったといわれる。
1939年9月1日のポーランド侵攻を境として、徴兵のために選手を揃えられないチームが続出し、やがてガウ・リーグの各チームは、以前のようなプレーの質を維持できなくなっていく。チームの存続自体が難しくなり、たとえ強豪であっても、兵役から一時帰休中の選手が偶然揃えば大勝するが、次の試合では選手が集まらずボロ負けする、というようなことが多々あったという。本来、選手は登録したチームでしかプレーできない規則であったのが、次第に兵隊であれば任地のチームでもプレーすることが許されるようになっていった。
そんな状況の中、全盛を誇っていたのがルール工業地方の雄シャルケ04である。1904年、ゲルゼンキルヘン市のシャルケ地区に創立されたことから命名されたこのクラブは、1933/34シーズンから、戦争末期の1943/44シーズンまで、常にガウ・ヴェストファーレン(ウェストファリア)のトップとして君臨し、この間なんと6度のドイツ・チャンピオンに輝いていた。
そんな「向かうところ敵なし」のシャルケ04に敢然と立ちはだかったのが、シェーン率いるDSCであった。1940年7月21日、ドイツ選手権準決勝に駒を進めたDSCは、シャルケと対戦する。会場のベルリン・オリンピックスタジアムには、10万人の観客がつめかけた。ゲームは一進一退の攻防をつづけ、延長戦でも決着がつかず3:3の引き分けに終わり、翌週の再試合となった。猛暑の中での熱戦により、シェーンは3,5キロも体重が落ち、直射日光にやられて気絶した観客も多数でたという。
現在のプロチームであれば、その後の1週間を休養と集中トレーニングに当てるのだろうが、当時のアマチュア選手達には、みな職場での通常業務が待っていた。選手達は、消耗した身体で列車に乗り、それぞれの故郷に戻るのであった。
翌週、シェーンとその仲間達は、十分な休養もままならないまま、再びベルリンまで遠征した。もっとも、相手のシャルケも条件は同じであったろう。むしろルール地方から来るシャルケ04の方が、移動距離は倍以上なのだ。試合は、残念ながら0:2のスコアで、DSCの敗北に終わった。
さらに、翌年のシーズンには、ついに決勝に進出したのだが、またしてもシャルケ04を相手に0:1の苦杯を喫した。2年連続で悔しい思いをしたとはいえ、チャンピオンシャルケと互角以上に渡り合ったDSCも、また大きな賞賛を受けるのであった。
戦時中の日本のプロ野球で、敵性用語である英語を廃止し、ストライクを「よし一本」、アウトを「退け」などと言い習わしたように、この頃になると、ドイツのサッカーで、英語式の用語を次々とドイツ風の表現に変えるという事態が起こっていた。ドイツ・サッカー連盟(DFB)も解体され、「国家社会主義体育協会」などという、わけのわからぬ組織に組み込まれていく。国全体が、既に抜き差しならぬヒステリックな状態に陥っていたのだ。ただ、それでもサッカーは続けられていた。
1943年になると、選手はもとより、物資の不足はさらに深刻な問題となる。破損したボールの代わりが見つからず試合が中止になるのも一度や二度ではなかったようだ。ユースチームやOBチームも総動員して、どうにか必要メンバーを揃えていたクラブもあり、チーム内に30歳以上年の離れた選手がいたこともあるという。通常の3分の2の大きさのフィールドに7名の選手でオフサイドはなし・・・という特別ルールが真剣に議論されたらしいが、結局は実施されなかった。
チームを維持する難しさは、王者シャルケ04とて例外ではなく、選手の保持に苦しみ、この年のドイツ選手権では1932年以来初めて準決勝を前に敗退していった。こうしていよいよDSCの時代がやってきた。
(敬称略、つづく)
|